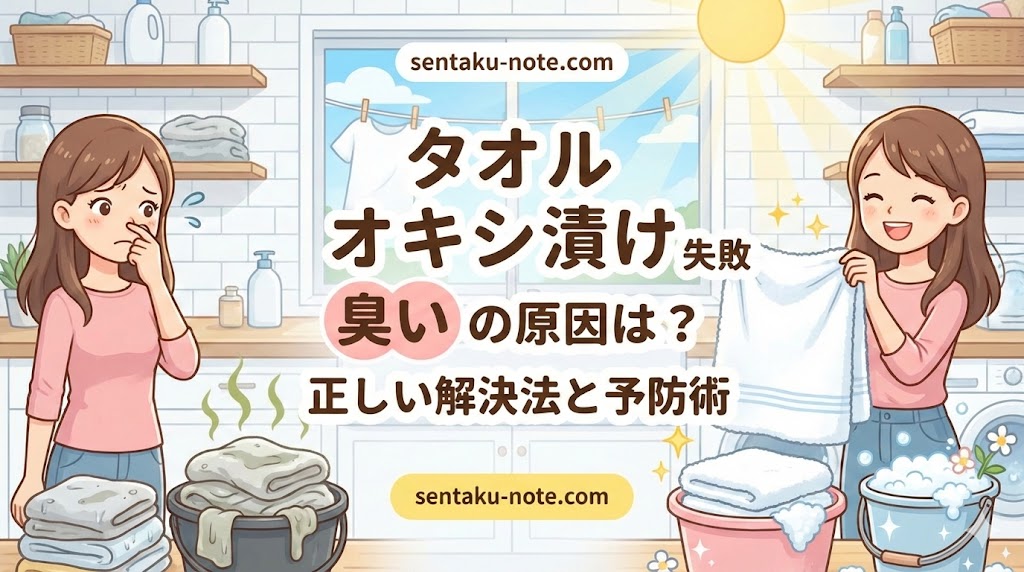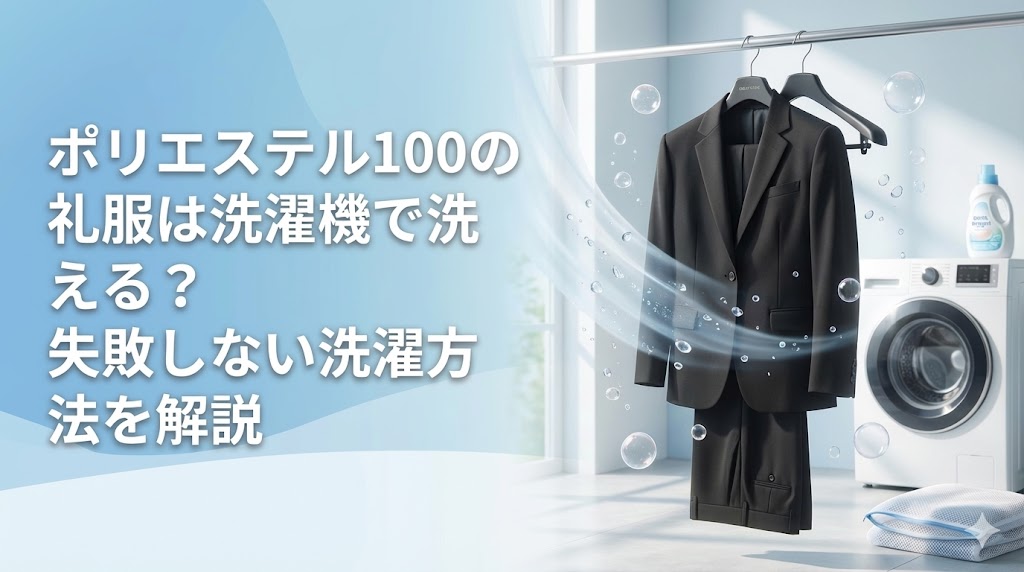※この記事にはプロモーションが含まれています。
急な入院が決まった時、治療への不安とともに頭をよぎるのが、着替えやタオルの洗濯といった日々の生活に関わる問題です。「入院中の洗濯物、一体どうしよう…」と、多くの人が頭を悩ませます。特に、ご家族が遠方に住んでいたり、仕事で忙しかったりして頼ることが難しい状況や、病院のコインランドリーが混雑していて使いにくい場合、「手洗い」で乗り切るという選択肢が現実味を帯びてきます。しかし、慣れない環境での手洗いは、何から手をつけて良いかわからないものです。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するため、入院中の洗濯はみんなどうしてる?という素朴な疑問から、具体的な手洗いのやり方、さらには100均で揃う便利なものまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。また、多くの人が直面する洗濯物を干す場所の問題や、病室という限られた空間で特に気になる部屋干しの臭い対策、そしてデリケートな問題である下着の洗い方にも深く踏み込んでいきます。
入院中の洗濯の頻度はどれくらいが適切なのか、病院のコインランドリーの上手な使い方、どうしても自分では難しい場合に入院中の洗濯を家族に頼むためのコツ、さらには長期入院での洗濯の乗り切り方まで、あらゆる状況を想定した解決策を網羅しました。この記事を最後まで読めば、入院中の洗濯に関するあらゆる悩みがすっきりと解消され、心穏やかに療養に専念できる環境を整えることができるはずです。
- 入院中の洗濯を手洗いする具体的な手順が、初心者でもわかるように理解できる
- 100均グッズなど費用を抑えつつ、洗濯の負担を劇的に軽くするアイテムがわかる
- 科学的根拠に基づいた部屋干しの嫌な臭いを防ぎ、衛生的に衣類を保つ方法がわかる
- 手洗い以外の選択肢(コインランドリーや家族)のメリット・デメリットと、上手に活用するコツがわかる
入院中の洗濯を手洗いで乗り切るための基本

- 入院中の洗濯はみんなどうしてる?
- 入院中に洗濯を手洗いする具体的なやり方
- 入院中の洗濯で100均で揃うものリスト
- 入院中の洗濯で使うおすすめの洗剤
- 入院中の洗濯で気になる下着の洗い方
- 入院中の洗濯はどれくらいの頻度で行う?
入院中の洗濯はみんなどうしてる?
入院という非日常の中で、他の患者さんが洗濯をどうしているのかは、意外と気になるポイントですよね。入院経験者へのアンケートなどを見ると、多くの人が状況に応じて複数の方法を使い分けていることがわかります。主な選択肢は、「①自分で手洗いする」「②病院のコインランドリーを利用する」「③家族や友人に頼む」という3つの方法です。
例えば、2〜3泊程度の短期入院であれば、入院日数分の着替えを多めに準備し、洗濯はせずに乗り切るという方が多数派です。しかし、入院が1週間以上に及ぶ場合、ほとんどのケースで何らかの洗濯が必要不可欠となります。
私自身が以前入院した際には、下着や靴下、ハンカチといった細々としたものは毎日洗面所で手洗いし、パジャマやバスタオルなどのかさばる物は、週末に面会に来てくれる家族にまとめて持ち帰ってもらう、というハイブリッド方式で対応していました。このように、ご自身の体調、入院期間、病院の設備(コインランドリーの有無や混雑状況)、そして家族の協力が得られるか否かといった様々な要因を考慮し、最適な方法を組み合わせることが、入院中の洗濯を乗り切る鍵となります。
【徹底比較】入院中の洗濯方法3つの選択肢
| 洗濯方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| ① 自分で手洗い | ・費用がほとんどかからない ・自分の好きなタイミングで洗濯できる ・少量の洗濯物にも対応しやすい | ・手間と時間がかかる ・体力を使う ・干す場所の確保が難しい ・厚手のものは乾きにくい | ・短期入院の方 ・費用を抑えたい方 ・家族に頼みにくい方 ・体力に比較的余裕がある方 |
| ② コインランドリー | ・乾燥機で素早く乾かせる ・生乾きの臭いの心配がない ・シーツなどの大物も洗える ・手間が少ない | ・利用料金がかかる(1回500円〜) ・利用時間が限られている ・他の患者さんと時間が重なり待ち時間が発生することも ・小銭の準備が必要 | ・長期入院の方 ・厚手の衣類や大物を洗いたい方 ・衛生面を重視する方 ・手洗いの手間を省きたい方 |
| ③ 家族に頼む | ・心身の負担が最も少ない ・自宅の洗濯機で清潔に洗ってもらえる ・費用がかからない | ・家族に手間と時間をかけさせてしまう ・面会のタイミングでしか頼めない ・家族が遠方だと頼めない ・頼むことに気兼ねしてしまう | ・家族が近くに住んでいる方 ・体調が優れず自分で動けない方 ・長期入院で洗濯物が多くなる方 |
どの方法が一番良い、という絶対的な正解はありません。それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、「平日は手洗い、週末は家族に」というように、柔軟に組み合わせていくのが最も賢明な方法と言えるでしょう。
入院中に洗濯を手洗いする具体的なやり方
入院中の手洗い洗濯は、慣れてしまえば療養生活のちょっとしたリズムにもなります。ここでは、洗面台や持参した洗面器を使って、衣類を傷めず、かつ効率的に汚れを落とすための具体的な手順を、プロの視点から詳しく解説します。作業の前には、感染症予防の観点からも、必ず石鹸で手を洗うか、手指消毒を行うことを徹底してください。
ステップ1:洗い 〜優しく、でも確実に汚れを落とす〜
まず、洗面台の栓をするか、用意したバケツや洗面器に30℃程度のぬるま湯を張ります。冷水よりもぬるま湯の方が皮脂汚れが格段に落ちやすいため、給湯器が使える場合はぜひ活用してください。次に、規定量の洗剤を入れ、手でよくかき混ぜて完全に溶かします。洗剤がダマになっていると、すすぎ残しの原因になるため、このひと手間が重要です。
洗濯物を投入したら、衣類を上から優しく押しては持ち上げる「押し洗い」を20〜30回繰り返します。この方法なら、生地への負担を最小限に抑えつつ、繊維の奥の汚れを押し出すことができます。特に汚れがひどい靴下の底や、シャツの襟・袖口などは、その部分を手のひらに乗せ、洗剤の原液を少量直接つけて、指の腹で優しく「もみ洗い」をすると効果的です。絶対に、生地同士をゴシゴシと強く擦り合わせないでください。繊維が傷み、毛玉や型崩れの原因となってしまいます。
ステップ2:すすぎ 〜洗剤残りを防ぐひと工夫〜
洗い終わったら、一度汚れた洗濯液をすべて捨てます。洗濯物を片手で軽く押さえて水を流すとスムーズです。そして、再びきれいなぬるま湯を張り、押し洗いと同じ要領で優しく押しながらすすぎます。この作業を最低でも2回、できれば3回繰り返しましょう。泡が出なくなり、水の濁りがなくなるのが目安です。すすぎが不十分だと、残った洗剤が肌への刺激になったり、黄ばみや臭いの原因になったりするため、丁寧に行いましょう。柔軟剤を使用する場合は、最後のすすぎの際に規定量を入れ、全体に行き渡らせるように軽く押してください。
ステップ3:脱水 〜タオルドライで乾燥時間を劇的に短縮〜
すすぎが終われば、最後の脱水工程です。洗濯機のようなパワフルな脱水は望めませんが、工夫次第で乾燥時間を大幅に短縮できます。まず、洗濯物を両手で優しく挟み込むようにして、上から押して水分を絞り出します。このとき、タオルを絞るようにねじってしまうのは厳禁です。衣類の繊維が伸びきってしまい、ヨレヨレになる原因になります。
そして、ここからが最大のポイントです。乾いた清潔なバスタオルの上に、水気を絞った洗濯物を広げて置きます。次に、バスタオルで洗濯物を挟み込むように端からクルクルと巻き寿司のように巻いていきます。最後に、その上から自分の体重をかけて、まんべんなくゆっくりと圧をかけます。これが「タオルドライ」です。驚くほどバスタオルが水分を吸収してくれるため、その後の乾燥時間が半分以下になることも。筆者であれば、このひと手間は療養中で体力がなくても、必ず行います。それくらい効果絶大なのです。
共有スペース利用の心得
病院の洗面台は、歯磨きや洗顔など、他の患者さんも利用する大切な共有スペースです。洗濯で長時間占領したり、床に水をこぼしてしまったりしないよう、最大限の配慮を心がけましょう。作業が終わったら、シンク周りを軽く拭き、髪の毛などが落ちていないか確認するくらいの心遣いができると素晴らしいです。
入院中の洗濯で100均で揃うものリスト

「入院中の洗濯のために、高価な道具を揃えるのはちょっと…」と感じる方は多いでしょう。ご安心ください。現在の100円ショップには、入院生活での洗濯を劇的に快適にする、アイデア満載の便利グッズが豊富に揃っています。ここでは、数ある商品の中から「これは絶対に買うべき!」と断言できる、厳選したアイテムをリストアップしてご紹介します。入院準備の際に、ぜひお近くの100円ショップを覗いてみてください。
【決定版】入院中の洗濯で活躍する100均神アイテム
| アイテム名 | 特徴と具体的な活用法 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 折りたたみバケツ・洗面器 | 使わない時はジャバラ状に折り畳め、厚さ数センチになる優れもの。病室の限られた収納スペースを圧迫しません。つけ置き洗いや、洗面台が使いにくい時の洗い桶として大活躍します。フックに掛けられる穴付きのものが便利です。 | 容量(5L程度が使いやすい)、折り畳みやすさ |
| 携帯用洗濯ロープ | 両端が吸盤やフックになっており、ベッド柵や窓枠、壁などに簡単に取り付けられます。ロープ自体がゴムでできていて、洗濯物をロープの隙間に挟んで干せるタイプなら、洗濯バサミが不要でさらに荷物を減らせます。 | 長さ、取り付け方法(吸盤かフックか) |
| 携帯用ハンガー(折りたたみ式) | こちらも使用しない時は手のひらサイズに折り畳める省スペース設計。数本持参すれば、パジャマやカーディガン、タオルなどを型崩れさせずに干せます。肩紐をかけられる溝や、洗濯バサミが付いている多機能タイプが特におすすめです。 | 折り畳んだ時のサイズ、肩紐フックの有無 |
| S字フック(大小セット) | 「万能選手」という言葉がぴったりのアイテム。ハンガーを吊るす、洗濯ネットや小物を入れたエコバッグをベッド柵に掛ける、濡れたタオルを一時的に干すなど、アイデア次第で無限の使い方ができます。サイズ違いで複数個持っていくと、必ず重宝します。 | 耐荷重、サイズのバリエーション |
| 仕切り付き洗濯ネット | 下着や靴下など、デリケートな衣類を洗う際の必需品。生地の傷みを防ぎ、他の洗濯物との絡まりも防止します。ネット内部に仕切りがあるタイプなら、左右で靴下を分けたり、下着の種類を分けたりでき、管理がしやすくなります。 | 目の細かさ(細かい方が衣類に優しい)、サイズ |
| 消臭機能付きビニール袋・チャック袋 | 洗い終わった濡れた洗濯物を一時的に入れたり、逆に汚れた衣類を次の洗濯まで保管したりするのに必須です。菌の増殖を抑える効果や消臭効果が謳われている製品を選ぶと、臭い対策としてさらに効果的です。 | サイズ、マチの有無、消臭・抗菌機能 |
これらのアイテムを揃えても、費用は1,000円以下に収まることがほとんどです。最小限の投資で、入院中の洗濯の快適さは格段に向上します。事前に準備しておくことで、いざという時に慌てずに済みますので、ぜひリストを参考にしてください。
入院中の洗濯で使うおすすめの洗剤
病室という特殊な環境で行う手洗いでは、洗剤選びも非常に重要な要素となります。洗浄力はもちろんのこと、持ち運びやすさ、溶けやすさ、そして周囲への配慮(特に香り)といった、普段の洗濯とは異なる視点での選択が求められます。ここでは、それぞれの特徴を踏まえ、入院中の洗濯に最適な洗剤タイプを徹底比較します。
【手軽さNo.1】シートタイプ・ジェルボールタイプ
計量が一切不要で、1回分が個別に包装されているため、持ち運びの手軽さと衛生面では他の追随を許しません。粉がこぼれる、液体が漏れるといったありがちなトラブルも皆無です。必要な回数分だけを小さなチャック袋に入れて持っていけば、荷物を極限までコンパクトにできます。特に、数日程度の短期入院や、洗濯の回数がそれほど多くない方には、このタイプが最も合理的でおすすめです。ただし、洗濯物の量に応じた微調整が効かない点は、唯一のデメリットと言えるかもしれません。
最近では各社から様々な製品が出ていますが、例えばライオンの「トップ スーパーNANOX 自動投入洗濯機用」のボトルは少量使いにも便利ですし、P&Gの「アリエール ジェルボール」シリーズは洗浄力の高さに定評があります。ご自身の使い慣れたブランドから選ぶのも良いでしょう。
【調整しやすさNo.1】液体洗剤
水への溶けやすさが抜群で、冷たい水でも洗剤残りの心配がほとんどないのが最大の利点です。洗濯物の量に合わせて、数滴単位での調整が可能なので、ハンカチ1枚だけを洗いたい、といったシーンにも柔軟に対応できます。市販のトラベル用ボトル(100均でも購入可能)に詰め替えて持参すれば、荷物がかさばることもありません。近年主流となっている「すすぎ1回」対応の濃縮タイプを選べば、節水と時間短縮に繋がり、体への負担も軽減できるため、入院中には特に大きなメリットとなります。
【洗浄力重視なら】粉末洗剤
一般的に、同量の液体洗剤よりも洗浄力が高いとされており、特に頑固な皮脂汚れや食べこぼしのシミなどに強いのが特徴です。ただし、低温の水には溶けにくく、溶け残りが衣類に付着することがあるため、必ずぬるま湯でしっかりと溶かしてから使用するのが鉄則です。こちらも、ダブルクリップなどで封ができる小さな袋に小分けにして持参すると便利です。
【最重要】香りのエチケットを忘れずに
病室は様々な患者さんが過ごす共同生活の場です。中には、化学物質過敏症の方や、治療の副作用で匂いに非常に敏感になっている方もいらっしゃいます。そのため、洗剤や柔軟剤は、可能な限り「無香料」または「微香性」と表示された製品を選ぶのが絶対的なマナーです。最近人気の「部屋干し用」と銘打たれた洗剤は、抗菌・防臭効果に特化しており、香りが控えめな製品が多い傾向にあるため、選択肢の一つとして有力です。自分にとっては心地よい香りでも、他人にとっては苦痛の原因になり得るということを、常に心に留めておきましょう。
入院中の洗濯で気になる下着の洗い方と干し方

入院生活において、下着の洗濯は衛生面を保つ上で欠かせない一方で、プライバシーの観点から特に気を遣う部分です。どうすれば清潔さを保ちつつ、人目を気にせずに洗濯から乾燥までを完結できるのか。そのための具体的な方法と、知っておきたい衛生管理のポイントを詳しく解説します。
デリケートな素材を守る「洗濯ネット」の活用
まず大前提として、下着を手洗いする際も、必ず洗濯ネットを使用しましょう。これは、レースなどの装飾や繊細な生地を、洗う際の摩擦から守り、型崩れやほつれを防ぐためです。100均などで手に入るもので十分ですので、下着専用のネットを用意することをおすすめします。洗面台で洗う際も、ネットに入れたままの状態で優しく押し洗いすることで、生地へのダメージを最小限に抑えることができます。また、洗濯物を持ち運ぶ際の目隠しとしても役立つ、一石二鳥のアイテムです。
見えないだけじゃない!衛生的な「つけ置き洗い」
もし経血などの血液が付着してしまった場合は、絶対にお湯を使わず、必ず冷たい水で洗い流すことが鉄則です。血液中のタンパク質は熱によって凝固する性質があるため、お湯をかけるとシミとして定着してしまいます。まずは流水で血液をできるだけ洗い流した後、洗剤を溶かした水に30分〜1時間ほどつけ置きします。それでも落ちない頑固な汚れには、液体タイプの酸素系漂白剤を少量加えることで、除菌と漂白の効果が期待できます。つけ置きは汚れを浮かせるだけでなく、菌の繁殖を抑える効果もあるため、衛生面からも非常に有効な方法です。
プライバシーを守る「干し方」の工夫
洗い終わった下着を干す工程は、最もプライバシーへの配慮が求められます。以下のテクニックを駆使して、スマートに乾燥させましょう。
- 定番の「隠し干し」:これは、持参したピンチハンガー(洗濯バサミがたくさん付いた物干し)の外周にバスタオルやフェイスタオルをぐるりと干し、その内側に下着類を干すというテクニックです。こうすることで、外からはタオルしか見えず、プライバシーを完璧に守ることができます。
- 「タオルサンド干し」:急いで乾かしたい場合におすすめなのがこの方法。乾いたタオルの間に下着を挟み、ハンガーにかけて干します。タオルの吸水効果で乾燥が早まる上、もちろん外から見えることもありません。
- 病室内の「死角」を探す:ベッドサイドのカーテンの陰や、クローゼットの中、許可されていれば洗面所の隅など、人目につきにくい「死角」となるスペースを見つけて干すのも一つの手です。ただし、必ず病院のルールを確認し、他の人の邪魔にならない範囲で行いましょう。
私の場合、小さなピンチハンガーとS字フックを持参し、ベッドの足元側の柵に「隠し干し」をしていました。この場所なら、自分のスペース内で完結し、通路側の視線も気になりません。清潔な下着を身につけることは、QOL(生活の質)の維持、ひいては治療へのモチベーションにも繋がる重要な要素です。少しの工夫で、この問題をスマートに乗り切りましょう。
入院中の洗濯はどれくらいの頻度で行う?
「入院中は、どれくらいのペースで洗濯すればいいんだろう?」これは、多くの人が抱く疑問です。しかし、この問いに「正解は週に〇回です」といった画一的な答えはありません。なぜなら、最適な洗濯頻度は、入院期間、季節、持参した衣類の枚数、そして何よりもご自身のその日の体調によって、大きく変動するからです。
入院期間から考える頻度の目安
- 1週間未満の短期入院の場合:この期間であれば、洗濯を一切せずに乗り切るのが最も現実的で、体への負担も少ない選択です。下着、靴下、タオル類を入院日数+予備2日分ほど準備しておけば、洗濯のことを考えずに療養に専念できます。ただし、夏場で汗を大量にかく、あるいは発熱で寝汗をかいた、といった場合には、肌着だけでもサッと手洗いすると、格段に快適に過ごせます。
- 1週間以上の長期入院の場合:長期戦になると、計画的な洗濯が必須となります。多くの入院経験者は、「2〜3日に1回、下着やタオルなどの小物を手洗いし、週に1〜2回、パジャマやトレーナーなどのかさばる物をコインランドリーでまとめて洗う」というペースに落ち着くようです。毎日洗濯をすると、それがかえってストレスや負担になることも。ある程度洗濯物を溜めてから、体調の良い日や時間帯を選んでまとめて行うのが、賢いやり方です。
洗濯の負担そのものを減らす工夫
療養中は、心身のエネルギーを回復に集中させることが最優先です。洗濯という家事に、貴重な体力を奪われないための工夫も大切になります。
【プロが教える】洗濯負担を軽減する衣類選びのコツ
入院準備の段階で、少し意識して衣類を選ぶだけで、入院中の洗濯は驚くほど楽になります。
- 速乾性のある機能性素材を選ぶ:ポリエステルなどの化学繊維でできたスポーツウェアやインナーは、綿素材に比べて圧倒的に乾きが早いです。夜に洗って干しておけば、翌朝には乾いていることも珍しくありません。
- 抗菌防臭機能付きを選ぶ:菌の繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぐ機能がある衣類は、部屋干しが基本となる入院中には最適です。洗濯の頻度自体を少し減らすことも可能になります。
- 使い捨てアイテムを賢く活用する:全てを洗濯で賄おうとせず、紙パンツや使い捨ての身体拭きシートなどを部分的に取り入れるのも、負担軽減に非常に有効です。特に術後など、体が思うように動かせない時期には重宝します。
繰り返しになりますが、最も大切なのは、ご自身の体調を最優先することです。「今日洗濯しないと」と義務感に駆られる必要はありません。辛いと感じる日は無理せず休み、体調が良い日に回す、あるいは可能であれば家族や友人に甘えるなど、柔軟な対応を心がけてください。あなたの体は、治療と回復が最優先事項なのですから。
入院中の洗濯を手洗い以外で解決する方法と注意点

- 入院中の洗濯物を干す場所に困ったら
- どうしても気になる洗濯物の臭い対策
- 病院のコインランドリーを上手に使う方法
- 入院中の洗濯を家族に頼む時のコツ
- 長期入院になった場合の洗濯はどうする?
- まとめ:快適な入院生活のための入院中 洗濯 手洗いの知識
入院中の洗濯物を干す場所に困ったら
手洗いが無事に終わった後、多くの人が「ラスボス」と呼ぶのが、この「物干し場所問題」です。病室という極めて限られたプライベートスペースで、どうすれば効率的に、そして周囲に迷惑をかけずに洗濯物を乾かせるのでしょうか。その解決策と、絶対に守るべきルールについて解説します。
【最優先事項】病院のルールを絶対的に確認する
具体的な場所を探す前に、何よりもまずやるべきことがあります。それは、入院している病院の「物干しに関するルール」を正確に確認することです。これは、快適性の問題だけでなく、安全管理上の極めて重要な事項です。例えば、火災報知器やスプリンクラーの作動を妨げる場所に物を干すことは厳禁ですし、避難経路の妨げになるような干し方も認められません。
ルールは「入院のしおり」に記載されているか、ナースステーションの壁に掲示されていることが多いです。もし不明な点があれば、必ず看護師さんに直接質問してください。自己判断でルールを破ってしまうと、他の患者さんとのトラブルや、病院スタッフからの厳しい注意を受ける原因となり、気まずい思いをすることになりかねません。
許可されている範囲内で見つける「物干しスペース」
病院のルールを遵守する、という大前提の上で、病室内で物干しスペースとして活用できる可能性のある場所をいくつかご紹介します。
- ベッドサイドやベッド柵:最も手軽で管理しやすいスペースです。持参したS字フックや洗濯ロープを柵に掛ければ、即席の物干しスペースが完成します。ただし、点滴スタンドや心電図モニターなどの医療機器に、濡れた洗濯物が触れたり、水滴が落ちたりしないよう、細心の注意を払う必要があります。
- 窓際やカーテンレール:日当たりが良く乾きやすいスペースですが、多くの病院ではカーテンレールへの物干しを禁止しています。レールの破損や、結露によるカビの発生原因となるためです。もし窓際に干す場合は、吸盤フックなどを利用し、窓ガラスや壁を汚さない工夫が求められます。
- 備え付けの椅子やテーブル:バスタオルなどの大きなものを広げて干すのに便利です。ただし、長時間占有すると本来の用途で使えなくなるため、短時間で乾かす工夫とセットで考えましょう。
- クローゼットやロッカーの扉:扉に掛けられるフックなどを利用すれば、目立たない物干しスペースになります。ただし、扉の開閉の邪魔にならないように配慮が必要です。
私が試して最も効率的だと感じたのは、USB電源で動く小型の「クリップ式扇風機」をベッド柵に取り付け、干した洗濯物に直接風を当てる方法です。空気の流れ(エアサーキュレーション)を作ることで、乾燥時間は驚くほど短縮され、生乾き臭の予防にも絶大な効果がありました。持ち込みが可能かどうかは、これも病院のルール確認が必要です。
多くの病院には、患者さんが自由に使えるデイルーム(談話室)が設置されています。日当たりの良い窓際に、共用の物干しスタンドが置かれている場合もあるので、一度チェックしてみる価値はあります。困った時は一人で悩まず、まずは看護師さんに「洗濯物を干したいのですが、どこか良い場所はありますか?」と相談してみましょう。きっと親身になってアドバイスをくれるはずです。
どうしても気になる洗濯物の臭い対策
病室での部屋干しにおいて、最大の敵となるのが、あのジメジメとした不快な「生乾き臭」です。嗅覚が敏感になりがちな療養中は、この臭いが想像以上に大きなストレスになります。ここでは、臭いの原因を科学的に理解し、洗濯の段階から臭いを元から断つための徹底的な対策をご紹介します。
臭いの正体は「モラクセラ菌」のフン
生乾き臭の原因は、雑巾のような臭いを発する「モラクセラ菌」という細菌です。この菌は、実は私たちの皮膚や口の中にもいる常在菌の一種なのですが、洗濯で落としきれなかった皮脂や汗、タンパク質汚れをエサにして増殖します。そして、増殖の過程で排出するフンが、あの不快な臭いの正体なのです。
モラクセラ菌は「水分」と「20〜40℃の温度」を好むため、濡れた洗濯物がゆっくり乾いていく過程は、彼らにとって絶好の繁殖環境となってしまいます。つまり、臭い対策の要点は、「①洗濯で菌のエサとなる汚れをしっかり落とすこと」と「②菌が増殖する時間を与えずに、いかに速く乾かすか」の2点に集約されます。
消費者庁も注意喚起!衣類のケア
衣類の表示を正しく理解し、適切にケアすることは、臭いや菌の繁殖を防ぐ基本です。消費者庁のウェブサイトでは、新しい洗濯表示の意味が詳しく解説されています。一度目を通しておくと、衣類を長持ちさせる上でも役立ちます。(参照:消費者庁「新しい洗濯表示」)
【予防策】臭いを発生させない洗濯術
- 「部屋干し用洗剤」を必ず使う:これはもはや必須アイテムです。部屋干し用洗剤には、モラクセラ菌の増殖を抑える抗菌剤や、菌のエサとなる皮脂汚れを強力に分解する酵素が配合されており、その効果は絶大です。
- 「酸素系漂白剤」の合わせ技:洗剤と一緒に、液体タイプの酸素系漂白剤を少量加えることで、殺菌・消臭効果が飛躍的に向上します。特に、臭いが染み付いてしまったタオルなどに効果てきめんです。
- 洗濯物を溜め込まない:汚れた洗濯物を洗濯カゴに長時間放置するのは、菌にエサを与えて培養しているようなものです。可能な限り、こまめに洗濯することを心がけましょう。
【乾燥術】菌が増える前に乾かしきる
- 徹底した「タオルドライ」:前述の通り、干す前の水分量を極限まで減らすことが、乾燥時間短縮への一番の近道です。
- 「アーチ干し」で風の通り道を作る:ピンチハンガーに洗濯物を干す際、両端に長いもの、中央に短いものを干す「アーチ型」に配置します。こうすることで、下に空間が生まれ、空気の通り道ができて効率的に乾きます。
- 小型扇風機・サーキュレーターの活用:もし持ち込みが許可されているなら、これほど強力な武器はありません。微風でも直接風を当て続けることで、水分の蒸発が促進され、乾燥時間を劇的に短縮できます。
- 仕上げの「除菌・消臭スプレー」:乾いた後、もし少しでも臭いが気になる場合は、衣類用の除菌・消臭スプレーを吹きかけておくと安心です。この場合も、香りが強くない製品を選びましょう。
これらの対策を一つひとつ丁寧に行うことで、入院中の部屋干し臭の悩みはほぼ解消できるはずです。清潔な香りの衣類に包まれて、少しでも心地よい時間をお過ごしください。
病院のコインランドリーを上手に使う方法

パジャマやバスタオル、シーツといった、手洗いでは手に負えない大物の洗濯や、梅雨時でどうしてもカラッと乾かしたい時に、救世主となるのが病院内に設置されたコインランドリーです。しかし、誰もが使う共有施設だからこそ、その使い方にはいくつかのコツと、守るべき大切なマナーが存在します。ここでは、コインランドリーをストレスなく、そしてスマートに使いこなすための完全ガイドをお届けします。
利用前に必ずチェックすべき4つのポイント
ランドリールームに着いたら、洗濯機にお金を入れる前に、まず以下の4点を必ず確認する習慣をつけましょう。
- 利用可能な時間帯:多くの病院では、夜間や早朝の利用を制限しています。通常は朝8時〜夜8時頃までが一般的ですが、病院によって異なるため、壁の掲示などで正確な時間を確認しましょう。
- 料金体系と使用可能な硬貨:洗濯機と乾燥機、それぞれの料金を確認します。「洗濯・乾燥一体型」の最新機種が導入されていることもあります。ほとんどの機械は100円玉専用です。いざという時に困らないよう、普段から100円玉を数枚、財布や小物入れに準備しておくと非常にスムーズです。両替機がない場合も多いので注意が必要です。
- 洗剤の有無と種類:洗剤が自動で投入されるタイプの洗濯機なのか、自分で用意する必要があるのかを確認します。洗剤持参型の場合、ランドリールーム内に自動販売機が設置されていることもありますが、割高なことが多いので、自分で用意していくのが経済的です。
- 洗濯槽の汚れチェック:前に使った人の汚れや、忘れ物が残っている可能性もゼロではありません。利用前に、一度洗濯槽の中をサッと覗いて確認する癖をつけておくと、より安心して使えます。
お互いが気持ちよく使うための「ランドリーマナー」
コインランドリーでのトラブルは、些細なマナー違反が原因で起こることがほとんどです。特に療養中は、小さなストレスも避けたいもの。以下のマナーを徹底し、スマートな利用を心がけましょう。
【最重要】洗濯物の長時間放置は絶対にNG!
コインランドリーで最もトラブルに発展しやすいのが、洗濯終了後の衣類の放置です。次に使いたい人が、あなたの洗濯物が終わるのをずっと待っているかもしれません。洗濯機や乾燥機を回したら、必ずスマートフォンのアラーム機能などを使い、終了時間きっかりに戻ってこれるようにしましょう。
もし体調が悪化するなどして、時間通りに戻るのが難しい場合は、無理に利用するのをやめるか、近くにいる看護師さんや家族に事情を話して、代理での回収をお願いするなどの対応が必要です。「少しくらい大丈夫だろう」という甘い考えが、大きなトラブルの火種になります。
- 洗濯物は詰め込みすぎない:汚れ落ちを良くし、機械の故障を防ぐためにも、洗濯物は容量の7〜8割程度にとどめるのが鉄則です。
- 利用後はセルフクリーニングを:乾燥機を使った後は、フィルターに驚くほどの量のホコリが溜まります。次の人が気持ちよく使えるように、備え付けのブラシなどでフィルターのホコリを必ず取り除いておきましょう。この小さな心遣いが、共有スペースの快適さを保ちます。
- 私物は必ず持ち帰る:洗濯カゴや洗剤、ハンガーなどをランドリールームに置きっぱなしにするのはやめましょう。紛失の原因になるだけでなく、他の利用者の邪魔になります。
ルールとマナーを守ることは、自分自身をトラブルから守ることにも繋がります。お互いに配慮し合い、譲り合いの精神で、この便利な設備を有効活用しましょう。
入院中の洗濯を家族に頼む時のコツ
もし、ご家族や親しい友人が協力を申し出てくれるのであれば、それに甘えるのが心身の回復のためには最善の選択です。しかし、その優しさにただ乗りかかるのではなく、頼む側としてできる限りの配慮をすることで、お互いの関係性をより良いものに保つことができます。「親しき仲にも礼儀あり」を胸に、相手の負担を少しでも軽くするための、賢い頼み方のコツをご紹介します。
すれ違いを防ぐ「事前ルール」の共有
「いつ、何を、どこで」受け渡しするのかが曖昧だと、せっかく来てくれたのにすれ違ってしまったり、必要なものが届かなかったり、といった残念な事態を招きかねません。そうしたストレスを防ぐため、事前に以下の点を具体的に話し合っておきましょう。
- 受け渡しの「曜日と時間」:「毎週火曜と土曜の面会時間にお願いできるかな?」というように、お互いの都合をすり合わせて、受け渡しのタイミングを固定化すると、生活リズムが作りやすくなります。
- 受け渡しの「場所」:感染症対策などで、病棟への立ち入りが制限されている場合もあります。病室で直接受け渡しができるのか、ナースステーションに預ける形式なのか、病院のルールを事前に確認し、伝えておきましょう。
- 洗い方の「リクエスト」の伝え方:「このセーターは乾燥機NGで」「これはネットに入れて洗ってほしい」といった特別なリクエストがある衣類は、それだけを別の袋に分け、袋にマジックでメモ書きをしておくと、口頭で伝えるよりも確実で、相手も忘れる心配がありません。
相手の負担を軽くする「3つの心遣い」
洗濯物をただ袋に詰めて渡すのではなく、ほんの少し手間を加えるだけで、引き受けてくれる側の負担は劇的に軽くなります。その一手間が、あなたの感謝の気持ちを伝える最良の方法です。
- 汚れがひどいものは「予洗い」しておく:血液や食べこぼしなどの頑固な汚れは、洗面所で軽く水洗いし、汚れを落としてから袋に入れましょう。他の洗濯物に汚れが移るのを防ぐ、衛生面での重要な配慮です。
- ポケットの中身は「空」にしておく:ティッシュやレシート、小銭などが入ったままになっていないか、渡す直前に全てのポケットを最終確認する癖をつけましょう。ティッシュが洗濯槽で悲惨な状態になった経験は、誰にでもあるはずです。それを未然に防ぐのは、頼む側の最低限の責任です。
- そして、最高の「ありがとう」を伝える:これが何よりも大切です。「いつも本当にありがとう。おかげですごく助かってるよ」という具体的な感謝の言葉を、目を見てしっかりと伝えましょう。あなたのその一言が、相手にとっては何よりの報酬となり、「また次も手伝ってあげたい」という温かい気持ちに繋がるのです。
家族や友人のサポートは、決して当たり前のものではありません。その貴重な優しさへの感謝を常に忘れず、お互いが気持ちよく協力し合える関係を築いていきましょう。
長期入院になった場合の洗濯はどうする?

当初は短期の予定だった入院が、思いのほか長引いてしまう。そんな時、日々の洗濯はより計画的かつ持続可能な方法で行う必要があります。短期入院の時と同じやり方では、体力的、時間的、そして経済的な負担が徐々に大きくなり、療養生活の質を下げてしまうことにもなりかねません。ここでは、数週間から数ヶ月に及ぶ長期戦を、洗濯のストレスを最小限に抑えて乗り切るための戦略的なアプローチをご紹介します。
「手洗い」と「コインランドリー」の賢い使い分け
長期入院において最も現実的でバランスの取れた方法が、「日常の小物は手洗い、週に数回の大物はコインランドリー」というハイブリッド戦略です。下着や靴下、ハンカチといった、毎日交換が必要で、かつ少量で洗えるものは、体調の良い日中にサッと手洗いします。そして、パジャマやトレーナー、バスタオルといった、かさばって乾きにくいものは、週に1〜2回、曜日を決めてコインランドリーで一気に洗濯から乾燥まで済ませてしまうのです。この方法なら、日々の細々とした負担をなくしつつ、コインランドリーの利用回数を抑えることで経済的な負担も管理できます。
【究極の選択肢】洗濯を完全にアウトソーシングする
もし経済的に許されるのであれば、「レンタルサービス(CSセット)」の利用は、長期入院におけるQOLを劇的に向上させる、非常に価値のある選択肢です。これは、専門業者がパジャマやタオル、日用品などを一式で提供し、使用済みのものは毎日〜数日に一度、清潔なものと交換してくれるという画期的なサービスです。
CS(ケア・サポート)セットとは?
多くの病院で導入が進んでいる、入院生活必需品のレンタルサービスのことです。料金は一日あたり数百円〜千円程度が相場ですが、プランによって内容は様々です。基本的な衣類・タオル類だけでなく、歯ブラシやシャンプー、ティッシュペーパー、食事用エプロンまで含まれるプランもあります。このサービスを利用する最大のメリットは、洗濯という行為から完全に解放されることです。これにより、洗濯物の管理や洗濯にかかる時間、体力、そして精神的な負担といった、あらゆるストレスから解放され、100%治療と回復に専念できる環境が手に入ります。
特に、ご家族のサポートが得られにくい方や、術後で体を動かすのが辛い方、あるいは少しでもストレス要因を減らして心穏やかに過ごしたいと考える方にとって、このサービスは費用以上の価値をもたらしてくれる可能性があります。ご自身の病院で利用可能かどうか、ぜひ一度、入院案内を確認したり、ナースステーションやソーシャルワーカーに問い合わせてみてください。
衣類の「スタメン」を見直す
長期入院では、持参する衣類のラインナップそのものを見直すことも、洗濯の負担を減らす上で非常に有効です。前述の通り、「速乾性」「抗菌防臭性」「シワになりにくさ」をキーワードに、高機能な衣類を選ぶことを強くおすすめします。少し値段は張るかもしれませんが、洗濯の回数を減らせたり、乾燥が早かったりすることで、結果的に時間と労力の節約に繋がります。「療養生活を快適にするための投資」と考え、入院準備の際にぜひ検討してみてください。
まとめ:快適な入院生活のための入院中 洗濯 手洗いの知識
この記事では、入院中の洗濯という、多くの人が直面する現実的な問題について、手洗いを中心に、あらゆる角度からその解決策を探ってきました。慣れない環境での洗濯は、確かに不安で面倒に感じるかもしれません。しかし、正しい知識とちょっとした工夫があれば、その負担は驚くほど軽くすることができます。清潔な衣類を身にまとうことは、衛生を保つだけでなく、心の健康を維持し、前向きな気持ちで治療に臨むための大切な要素です。最後に、快適な入院生活を送るための入院中 洗濯 手洗いの重要なポイントを、改めてリスト形式で振り返りましょう。
- 入院中の洗濯方法は主に手洗い・コインランドリー・家族に頼むの3択
- 手洗いは押し洗いともみ洗いが基本でゴシゴシ擦らない
- すすぎは2〜3回行い洗剤が残らないようにする
- 脱水はタオルドライを行うと乾きが格段に早くなる
- 100均の折りたたみバケツや携帯ロープは入院中の洗濯で大活躍する
- 洗剤は計量不要なシートタイプやジェルボールが持ち運びに便利
- 香りの強い洗剤や柔軟剤は避け無香料や微香性を選ぶのがマナー
- 下着は洗濯ネットに入れて洗いタオルで隠し干しするなどプライバシーに配慮する
- 洗濯の頻度は体調を最優先し無理のない範囲で行う
- 洗濯物を干す場所はまず病院のルールを確認することが最も重要
- 生乾き臭対策には部屋干し用洗剤の使用と風通しを良くすることが効果的
- コインランドリーは利用時間を守り洗濯終了後は速やかに取り出す
- 家族に頼む際は感謝の気持ちを伝え洗濯物の分別など配慮を忘れない
- 長期入院ではレンタルサービスの活用も有効な選択肢
- 乾きやすくシワになりにくい衣類を選ぶと洗濯の負担を軽減できる
この情報が、あなたの入院生活における不安を少しでも和らげ、心穏やかな療養の助けとなることを心から願っています。