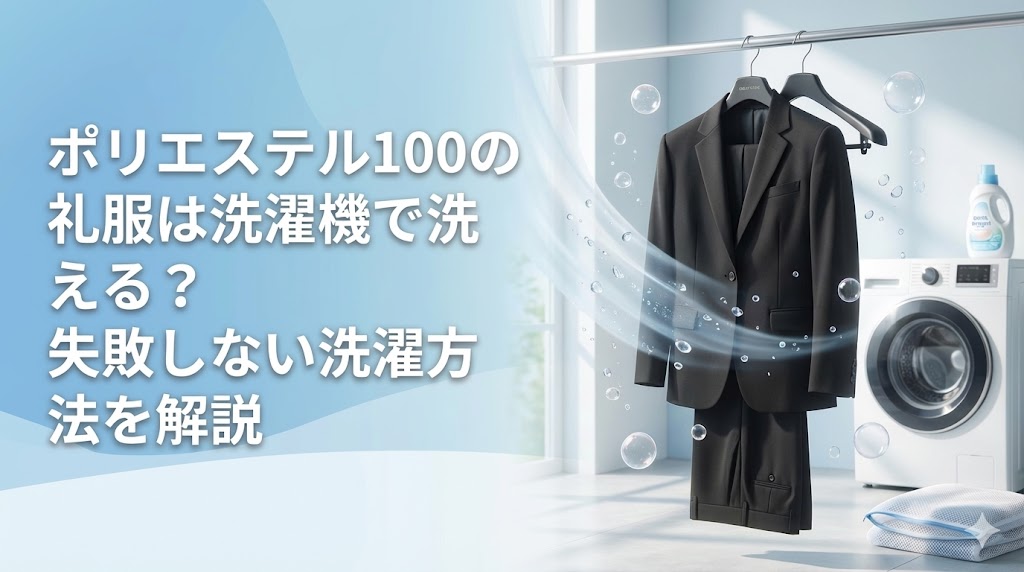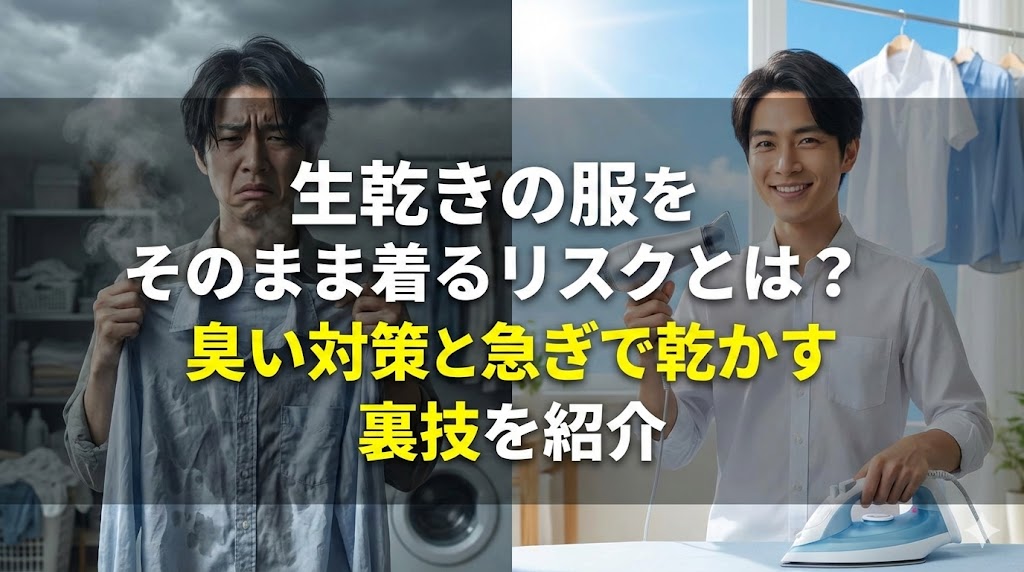※この記事にはプロモーションが含まれています。
コインランドリーを利用する際、「洗濯乾燥一体型」と「洗濯機と乾燥機を別々に使う」のでは、どちらが安いのか悩んだことはありませんか?
料金だけを見ると別々の方が安く感じますが、一体型の手軽さも捨てがたいものです。特に雨の日が続いて洗濯物が溜まってしまった時や、シーズンオフの毛布などの大物を洗濯する時、「結局、どちらが自分にとって一番お得なんだろう?」と、機械の前で迷ってしまう方も少なくないでしょう。
数百円の違いであっても、頻繁に利用するとなれば大きな差になります。しかし、安さだけを追求して手間のかかる方を選び、かえって時間を浪費してしまっては本末転倒です。
この記事では、コインランドリーの洗濯乾燥機との料金比較はもちろん、洗濯のみや乾燥だけの料金相場、さらに洗濯乾燥別で利用する場合の具体的な料金と時間について、あらゆる角度から深く掘り下げて詳しく解説します。
また、コインランドリーで洗濯乾燥別を選ぶメリットとデメリット、一体型が高いと言われる理由にも鋭く迫ります。さらに、多くの人が経験する「コインランドリーの洗濯乾燥機が乾かない」という最悪の事態を避けるための対処法や、かさばる毛布をふんわり仕上げるための洗濯乾燥の使い方、そして筆者自身が実践している具体的なコインランドリーの節約術まで、徹底的に網羅しました。この記事を読めば、あなたのライフスタイルや洗濯物の量に最適な、コインランドリーで賢く安く済ませる方法が必ず見つかります。
- 洗濯乾燥一体型と別々利用時の料金・時間の詳細な比較
- 洗濯のみ・乾燥のみの具体的な料金相場と活用シーン
- 洗濯物の量や種類(毛布など)に応じた最適な機械の選び方
- 今日から実践できる、コインランドリーの料金を安く抑えるための具体的な節約術
コインランドリー洗濯乾燥別は安い?一体型と比較

コインランドリーの利用で「洗濯乾燥別は本当に安いのか」は、多くの人が疑問に思う最重要ポイントです。結論から言えば、多くの場合で「別々」に利用する方が総額は安くなりますが、それには明確な理由があります。
しかし、料金だけで判断すると「濡れた重い洗濯物を移し替える手間」や「洗濯完了を待つ拘束時間」といった、目に見えないコストを見落とすことになります。ここでは、一体型との詳細な比較やそれぞれの料金相場、メリット・デメリットを徹底的に解剖していきましょう。
- コインランドリー洗濯乾燥機との料金比較
- コインランドリー洗濯のみの料金相場
- コインランドリー乾燥だけの料金相場
- コインランドリー洗濯乾燥別でかかる料金と時間
- コインランドリー洗濯乾燥別のメリットとデメリット
- コインランドリー一体型が高い理由
コインランドリー洗濯乾燥機との料金比較
コインランドリーの機械は、大きく分けて「洗濯から乾燥までノンストップで行う一体型」と、「洗濯機」と「乾燥機」が別々になっているセパレートタイプがあります。
どちらを選ぶかで、料金、所要時間、手間、そして仕上がりが大きく変わってきます。それぞれの特徴を深く理解することが、賢いコインランドリー活用への第一歩です。まずは、両者の違いを明確に比較した表をご覧ください。
| 比較項目 | 一体型(洗濯乾燥機) | セパレート(洗濯機+乾燥機) |
|---|---|---|
| 料金相場(中量) | 約1,000円〜1,200円(洗濯〜乾燥 約60分) | 約700円〜1,000円(洗濯機400円+乾燥機30分300円など) |
| 所要時間 | 約60分〜80分(コース固定) | 約60分〜(洗濯約30分+乾燥約30分〜) ※乾燥時間は自分で調整可能 |
| 手間 | 最小(放置できる) 洗濯物を入れるだけ。完了まで外出可能。 | 多い(移し替え必須) 洗濯完了後、濡れた洗濯物を乾燥機へ移す作業が発生。 |
| 仕上がり(乾燥) | 機種による(ややムラが出やすいことも) 乾燥容量が洗濯容量より小さい場合、詰め込むと生乾きリスクあり。 | 非常に良い(高温ガスでふんわり) 専用乾燥機のためパワーが強く、殺菌・ダニ対策効果も高い。 |
| 柔軟性・拡張性 | 低い(コースが固定) 「乾燥だけ10分追加」などが難しい機種が多い。 | 非常に高い(乾燥時間を10分単位で調整可) 洗濯物の量や種類に応じ、最適な乾燥時間を選べる。 |
このように、料金面だけを純粋に比較すると、セパレート(別々)に軍配が上がることが多いです。その最大の理由は、「乾燥時間を自分で完璧にコントロールできる」という柔軟性の高さにあります。洗濯物が薄手で乾きやすければ、乾燥時間を20分(200円)で切り上げることも可能です。
一方で、一体型は洗濯物を移し替える手間が一切なく、一度設定すれば完了まで完全に店舗を離れることができます。「買い物や用事のついでに洗濯を済ませたい」「寒い冬に濡れた洗濯物を触りたくない」という方にとって、この「放置できる」という利便性は、数百円の価格差を上回る価値があるとも言えます。
また、乾燥方式の違いも重要です。セパレートの乾燥機はほぼ100%が「ガス式」で、高温・大風量で一気に乾かします。一方、一体型は機種により「ヒートポンプ式」や「水冷除湿式」などがあり、ガス式に比べて乾燥時間がやや長くなる(=料金が上がる)傾向があります。
私の場合、時間に余裕がある週末や、タオルの仕上がりにこだわりたい時、アレルギー対策でダニをしっかり退治したい時は、迷わず「セパレート」を選びます。逆に、仕事で疲れている平日の夜などは、多少高くても「一体型」で手間を最小限に抑えるなど、状況に応じて賢く使い分けています。
コインランドリー洗濯のみの料金相場
コインランドリーで洗濯機だけを利用する場合の料金は、洗濯機の容量(kg)によって決まるのが一般的です。容量が大きくなるほど、一度に洗える量が増え、料金も上がります。この「洗濯のみ」の利用は、特に自宅で干す場所がある方にとっては、強力な節約手段となります。
店舗や地域によって差はありますが、おおよその料金相場と容量の目安は以下の通りです。
- 小型(約7kg〜10kg):300円〜400円 (目安:一人暮らしの3〜4日分、Tシャツ約30〜40枚程度)
- 中型(約12kg〜17kg):500円〜700円 (目安:2〜3人家族のまとめ洗い、薄手の毛布1〜2枚、ダブルの掛け布団カバーなど)
- 大型(約20kg〜32kg):800円〜1,200円 (目安:4人以上の家族、羽毛布団1〜2枚、こたつ布団セット、毛布3枚以上)
「洗濯だけ」をコインランドリーで行うメリットは、単に量が多い時だけではありません。
「洗濯だけ」利用の隠れたメリット
1. 圧倒的な洗浄力(お湯洗い) 家庭用洗濯機の多くは「水洗い」ですが、コインランドリーの機械は機種によって「お湯洗いコース」が選択できます。皮脂汚れや油汚れ、ニオイの原因菌は、水よりもお湯の方が格段に落ちやすくなります。ワイシャツの襟袖汚れや、作業着の頑固な汚れにも効果的です。
2. 「半ランドリー」という選択肢 特に梅雨時期や花粉の季節、PM2.5が気になる日など、外干ししたくない時に「洗濯だけ」コインランドリーで行うのは非常に賢い選択です。コインランドリーの洗濯機は家庭用より脱水力も強力なため、その後の部屋干し時間が劇的に短縮され、生乾き臭の原因となる雑菌の繁殖を抑えることができます。
現在のコインランドリーの洗濯機(および洗濯乾燥機)は、その多くが洗剤・柔軟剤自動投入型です。そのため、基本的には手ぶらで行っても洗濯が可能です。ただし、店舗によっては旧型の機械が設置されている場合や、アレルギーなどで特定の洗剤を使いたい方向けの「洗剤なしコース」が用意されていることもあります。
コインランドリー乾燥だけの料金相場
コインランドリーの乾燥機は、その多くがパワフルなガス式です。家庭用の電気式乾燥機(特にドラム式洗濯乾燥機)とは比べ物にならないスピードとパワーで、洗濯物をふんわりと仕上げてくれます。この「乾燥だけ」の利用こそ、コインランドリーの価値を最大限に引き出す使い方かもしれません。
料金は容量(kg)と時間(分)によって決まります。多くの店舗では「100円で何分」という、非常に分かりやすい料金体系が採用されています。
- 中型(約14kg):100円 / 約10分〜12分
- 大型(約25kg):100円 / 約8分〜10分
「大型の方が100円あたりの時間が短い?」と疑問に思うかもしれませんが、これは大型の方がパワーが強く、熱効率が良いため、実質的な乾燥スピードは大型の方が早いことが多いためです。パンパンに詰め込むより、大型でゆったり乾かす方が結果的に総額が安くなることもあります。
一般的な洗濯物(中型機で洗濯した場合)であれば、約30分(300円程度)で十分に乾かすことができます。ジーンズなどの厚手のものが多い場合や、毛布などは40分〜50分(400円〜500円)ほど見ると安心です。
乾燥機だけを利用する最大のメリットは、この「乾燥時間と料金の完璧な柔軟性」です。洗濯物の乾き具合を途中で確認しながら100円ずつ追加できるため、無駄なコストを徹底的に省くことが可能です。これが、「洗濯乾燥別が安い」と言われる最大の理由です。
ガス式乾燥機の圧倒的メリット(ダニ対策)
コインランドリーのガス乾燥機は、約80℃以上の高温(機種によります)で一気に乾燥させます。これにより、家庭では難しい以下のようなメリットが生まれます。
- ふんわり仕上げ:短時間で乾かすため繊維が立ち上がり、特にタオルのパイルが復活し、ホテルのような仕上がりになります。
- 強力な殺菌・ダニ対策:高温により、生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌など)を殺菌します。さらに、布団や毛布に潜むダニ対策にも極めて効果的です。厚生労働省の「アレルギー疾患対策の推進に関する検討会報告書」においても、アレルゲン対策として「50℃以上、20分以上」の加熱が推奨されており、コインランドリーの高温乾燥はこれをクリアする有効な手段です。
- 時間短縮:家庭用電気式で数時間かかる量が、わずか30〜40分で完了します。
コインランドリー洗濯乾燥別でかかる料金と時間

では、実際に洗濯機と乾燥機を別々に利用した場合のトータル料金と時間を、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。一体型と比較した場合の差額にも注目してください。
【ケース1:一人暮らしの3日分の洗濯物(約5kg)】
- セパレート(別々)の場合
- 洗濯機:小型(10kg)利用 → 400円 / 約30分
- 乾燥機:中型(14kg)利用 → 300円 / 約30分(薄手が多いと仮定)
- 合計:約700円 / 約60分(+移し替えの手間 約5分)
- 一体型の場合
- 洗濯乾燥機:少量コース利用 → 約800円〜1,000円 / 約60分
→ このケースでは、セパレート(別々)の方が100円〜300円程度安くなる可能性が非常に高いです。洗濯物の量が少ないほど、乾燥時間の調整が効くセパレートが有利になります。
【ケース2:家族3人分の週末まとめ洗い(約10kg)】
- セパレート(別々)の場合
- 洗濯機:中型(17kg)利用 → 600円 / 約30分
- 乾燥機:大型(25kg)利用 → 400円 / 約30分(大型の方が効率が良い)
- 合計:約1,000円 / 約60分(+移し替えの手間 約5分)
- 一体型の場合
- 洗濯乾燥機:標準コース利用 → 約1,000円〜1,200円 / 約60〜80分
→ このケースでは、料金は同等か、最大200円程度安くなります。もし洗濯物が乾きやすい素材なら、乾燥を20分(200円〜300円)で終えられれば、節約効果はさらに高まります。
所要時間については、洗濯と乾燥を別々に行うため合計時間は長くなりそうですが、実際は洗濯機が約30分、乾燥機が約30分と、一体型の標準コース(約60分)と大差ないか、むしろ早い場合もあります。ただし、このシミュレーションには「移し替えの手間 約5分」が加わります。濡れた洗濯物(特に10kg)は非常に重く、それを運ぶ労力は無視できません。この手間をどう捉えるかが、コストとの天秤になります。
コインランドリー洗濯乾燥別のメリットとデメリット
料金や時間以外の側面も含めて、洗濯乾燥別で利用する場合のメリットとデメリットを深く掘り下げて整理します。この比較が、あなたの最終的な選択を左右するかもしれません。
メリット
- 料金が安くなる可能性が高い(最大のメリット) 前述の通り、乾燥時間を100円単位で細かく調整できるため、トータルコストを抑えやすいです。乾きやすい衣類なら20分で切り上げる、といった柔軟な対応が最大の強みです。「乾燥させすぎ」による衣類の傷みも防げます。
- 乾燥性能が非常に高く、仕上がりが良い セパレートの乾燥機は高温のガスで一気に乾かすため、仕上がりが「ふんわり」します。タオルのパイルが立ち上がり、ホテルのタオルのような質感になります。また、高温による殺菌・脱臭・ダニ退治効果も、一体型(乾燥方式による)より高いとされています。
- 洗濯と乾燥を同時に行える(上級テク) これは大量の洗濯物をこなす際の最強テクニックです。洗濯物が大量にある場合(例:2台分の洗濯物)、1台目で洗濯機(30分)を回し、終わったらそれを乾燥機(30分)に移すと同時に、2台目の洗濯機(30分)を回すことができます。これにより、60分で2回分の洗濯・乾燥を終えることが可能です。
- 容量の選択肢が広い 「洗濯は中型、乾燥は大型」といったように、洗濯物の量や種類に応じて最適なサイズの機械を選べます。特に乾燥は、大きめの機械でゆったり乾かす方が効率が良いため、このメリットは大きいです。一体型だと、洗濯容量に合わせた固定サイズしか選べません。
デメリット
- 手間がかかる(最大のデメリット) 最大のデメリットは「手間の発生」です。洗濯が完了したら、濡れて重くなった洗濯物(水分を含んで10kg超)を一度取り出し、カートで乾燥機まで運び、再び投入する作業が発生します。これが面倒で一体型を選ぶ人も多いです。
- 待ち時間が発生する(拘束時間) 洗濯完了のタイミング(約30分後)で店舗にいなければなりません。一体型のように「60分後にまた来よう」という使い方がしにくく、店舗での待機時間が発生します。この30分を有効活用できないと、時間的コストは高くなります。
- 機械が空いていないリスク 洗濯が終わったタイミングで、使おうと思っていた乾燥機がすべて使用中という可能性もあります。特に雨の日や週末の午前中は「乾燥機難民」が発生しやすく、洗濯機から出した洗濯物を持って待たなければならない最悪の状況も起こり得ます。
コインランドリー一体型が高い理由
一体型の洗濯乾燥機は、セパレート利用に比べて総額が割高になる傾向があります。その理由は、単に「便利だから」だけではなく、機械の構造や料金設定にも起因しています。
1. 乾燥方式の違いと所要時間 一体型の乾燥方式は、セパレートのガス式と異なる場合があります(ヒートポンプ式や水冷除湿式など)。これらの方式はガス式に比べて熱効率がやや劣る場合があり、洗濯槽の中で乾燥まで行うには時間がかかりがちです。結果として、標準コースの時間が60分や80分と長めに設定されており、その分料金が高くなります。
2. コース料金設定の不柔軟さ 一体型は「洗濯のみ(400円)」「洗濯〜乾燥 標準(1,000円)」「洗濯〜乾燥 少量(800円)」といったコース料金があらかじめ決まっています。 セパレートであれば「洗濯400円+乾燥200円=600円」で済むような少量の洗濯物でも、一体型では「少量コース800円」を選ばざるを得ません。また、「乾燥だけ10分延長」といった柔軟な調整ができない機種も多く、乾燥が不十分だと感じても、追加で高額な「乾燥コース(30分300円など)」を選ぶしかなく、結果的に割高になることがあります。
3. 利便性の対価(最大の理由) 前述のデメリット(手間・待ち時間)をすべて解消してくれるのが一体型です。洗濯物を移し替える必要がなく、完了まで完全に放置できるという「時間的価値」と「労力の削減」に対して、セパレート利用よりも100円〜300円高い料金が設定されている、と考えるのが最も妥当でしょう。 「時は金なり」の観点から見れば、この料金差は「時間を買う」ためのコストと言えます。特に、共働き世帯や小さなお子様がいるご家庭、多忙なビジネスパーソンにとっては、合理的な選択となります。
結論:どちらを選ぶべきか
- 安さと乾燥の仕上がりを徹底追求するなら: セパレート(別々)がおすすめです。特に時間に余裕があり、乾燥時間をこまめに調整する手間を惜しまない人に向いています。
- 手間を省きたい・時間を有効活用したいなら: 一体型(洗濯乾燥機)がおすすめです。多少高くても、移し替えの手間を省き、待ち時間なしで外出したい多忙な人に向いています。
コインランドリー洗濯乾燥別を安く使うコツ

コインランドリー洗濯乾燥別は安いとはいえ、使い方を工夫すればさらに節約が可能です。ここでは、乾燥機が乾かない時の対処法から、毛布などの大物の洗い方、そして筆者が実践する節約術まで、安く使うための具体的なコツを詳しく紹介します。これらのテクニックを駆使すれば、あなたのコインランドリー代は確実に変わります。
- コインランドリー洗濯乾燥別の使い方
- コインランドリーの洗濯乾燥機が乾かない対処法
- コインランドリーで毛布を洗う時の使い方
- 私が実践するコインランドリーの節約術
- コインランドリーで安く済ませる方法
- コインランドリー洗濯乾燥別を安く使う総まとめ
コインランドリー洗濯乾燥別の使い方
セパレートタイプを賢く使い、その「安さ」というメリットを最大限に引き出すための基本的な流れと、プロ目線のコツを再確認しましょう。この手順を守るだけで、無駄な出費を抑えられます。
- 洗濯機を選ぶ(容量の7〜8割) 洗濯物の量の7〜8割程度の容量が目安です。詰め込みすぎは洗浄力が低下し、すすぎ残しの原因にもなります。逆にスカスカすぎてもコストの無駄になるため、適切なサイズを選びます。迷ったら、ワンサイズ上を選ぶ方が失敗は少ないです。
- 洗濯コースを選ぶ(約30分) 標準コースで約30分程度です。洗剤や柔軟剤は自動投入がほとんどですが、念のため確認しましょう。汚れがひどい場合は「お湯洗い」コースを選びます。
- 洗濯完了・迅速に移動 洗濯が終わったら、速やかに取り出します。他の方が待っている場合もあるため、洗濯完了時間を見計らって機械の前に戻るのがマナーです。この時、備え付けのカートを使うと移動が楽です。
- 乾燥機を選ぶ(洗濯機より大きいサイズが鍵) ここが非常に重要なコツです。洗濯機より一回り大きい容量の乾燥機を選んでください。例えば、12kgの洗濯機を使ったら、14kgではなく25kgの乾燥機を選ぶイメージです。なぜなら、庫内にスペースがあり、洗濯物が大きく舞う方が熱風がよく循環し、結果的に早くふんわり乾くからです。
- 乾燥時間を設定する(100円ずつ追加が最強) まずは「20分(200円)」など、明らかに乾ききらないだろうという短めの時間で設定します。終了後に乾き具合を確認し(特に厚手のものの縫い目など)、必要なら「10分(100円)」ずつ追加していくのが最も賢く、無駄のない使い方です。最初から「50分」と設定するのは避けるべきです。
私の場合、洗濯物が少ない時や薄手の衣類が多い時は、まず20分だけ乾燥させます。Tシャツや下着類は大抵これで乾くので先に取り出して畳み始め、乾ききっていないジーンズや厚手のタオルだけをカゴに入れ、もう100円追加して(時には小型の乾燥機に移し替えて)仕上げる、といった工夫もします。この「仕分け」と「こまめな追加」が節約に直結します。
コインランドリーの洗濯乾燥機が乾かない対処法
一体型やセパレート(別々)を問わず、「設定時間通りに終わったのに乾いていない」「生乾きだ」という事態は、最も避けたい追加コストの発生源です。乾かない時の主な原因と、それを防ぐための対処法を知っておきましょう。
主な原因
- 洗濯物の詰め込みすぎ(最重要) 最も多い原因です。特に乾燥は、容量オーバーだと熱風が全体に行き渡らず、洗濯物が団子状になってしまい乾きムラができます。一体型は乾燥時の容量が洗濯時より小さい(例:洗濯12kg/乾燥8kg)場合が多いので、この「乾燥容量」を必ず確認してください。洗濯容量の7割程度が乾燥の適量と考えるべきです。
- フィルターの目詰まり 乾燥機の奥にあるフィルター(リントフィルター)にホコリが溜まっていると、空気の循環が著しく悪くなり、乾燥効率が低下します。これは利用者のマナーとして、使用前に確認・清掃するのがベストです。
- 厚手のものと薄手のものの混在 ジーンズの腰回りやパーカーのフード部分と、薄手のTシャツでは乾くスピードが全く違います。これらが混在していると、厚手のものに合わせて時間を設定する必要があり、薄手のものは過乾燥で傷み、厚手のものは生乾き、という最悪の結果になりがちです。
対処法
- 乾燥機に入れる量を減らす(8割以下目安) これが最も効果的です。乾燥機は、洗濯槽の中で洗濯物がふんわりと舞うスペースがある方が早く乾きます。迷ったら、一回り大きな乾燥機を選ぶのが正解です。
- 乾燥フィルターを掃除する 乾燥機に入れる前に、必ずフィルターを確認し、備え付けのブラシなどで掃除しましょう。前の利用者のホコリがびっしり詰まっていることも珍しくありません。
- 【裏ワザ】乾いたバスタオルを入れる 乾燥機を回す際に、乾いた清潔なバスタオルを1枚一緒に入れると、タオルが湿気を素早く吸い取り、全体の乾燥時間を短縮できると言われています。
- 途中で一度かき混ぜる(特に大物) 乾燥時間の途中で一度扉を開け(一時停止し)、洗濯物が団子状になっていないか確認し、かき混ぜてほぐすだけでも乾きムラを劇的に防げます。特にシーツや長ズボンは絡まりやすいので有効です。
洗濯表示の確認は自己責任です
コインランドリーの高温乾燥は強力ですが、熱に弱い素材(ウール、シルク、レーヨン、装飾のある服など)や、縮みやすい衣類(綿Tシャツ、スウェットなど)には使えません。衣類が縮んだり、プリントが剥がれたり、傷んだりしても、それは自己責任となります。
必ず洗濯表示の「タンブル乾燥(四角に丸)」のマークを確認してください。バツ印が付いているものは、コインランドリーの乾燥機は絶対に使用できません。「低温(・)」の指定があるものも注意が必要です。
(参照:消費者庁「新しい洗濯表示」)
コインランドリーで毛布を洗う時の使い方

コインランドリーが最も活躍するのが、毛布や布団、こたつ布団などの大物洗いです。家庭では絶対に不可能な「丸洗い」と「高温乾燥」が実現できます。これらも、洗濯と乾燥を別々に行い、特に「乾燥」にこだわるのが成功の秘訣です。
毛布の洗濯・乾燥の完全手順
- 洗濯機の選定(容量に余裕を) 毛布1枚なら中型(12kg〜17kg)、2枚なら大型(20kg以上)の洗濯機を選びます。洗濯槽の7〜8割程度の余裕を持たせることが、中綿までしっかり洗うためのポイントです。素材(アクリル、ポリエステル、綿)も確認しましょう。
- 毛布の入れ方(屏風畳み) そのまま詰め込むのはNGです。毛布を縦に長く広げ、屏風畳み(ジグザグ)に畳んでから、洗濯槽のカーブに沿わせるように丸めて入れると、中まで水と洗剤が浸透しやすくなり、洗いムラを防げます。
- 洗濯コースの選択(約30分) 洗濯機に「毛布コース」があればそれを選びます。なければ標準コースで問題ありません。約30分で洗濯・脱水が完了します。
- 乾燥機への移動(最重要ステップ) ここが最重要ポイントです。乾燥機は、洗濯機よりもさらに一回り大きなサイズ(例:25kg大型乾燥機)を選んでください。毛布が大きく広がり、ふんわりと回転できるスペースがなければ、中まで絶対に乾きません。
- 乾燥時間の設定(40分〜60分目安) 毛布の素材によって必要な時間が変わります。まずは30分〜40分設定し、その後は10分ずつ追加するのが安全です。
| 素材 | 目安時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| アクリル・ポリエステル | 約30分〜40分 | 化学繊維は乾きやすい。 |
| 綿(コットン) | 約50分〜60分 | 天然繊維は水分を含みやすく、乾きにくい。 |
| 羽毛布団 | 約60分〜80分 | 中までしっかり乾かすのに時間がかかる。 |
【裏ワザ】途中で裏返す 20分ほど経過したら一度取り出し、裏返したり畳み直したりして、乾いていない部分が外側に来るようにして入れ直すと、乾きムラを完璧に防げます。
生乾きのまま持ち帰ると、カビや不快な臭いの原因となり、せっかくの洗濯が台無しになります。毛布こそ、ケチらずに「完全に乾かしきる」ことが何よりも重要です。
私が実践するコインランドリーの節約術

筆者もコインランドリーを頻繁に利用しますが、その際に必ず実践している「100円を浮かせる」ための節約術をいくつかご紹介します。これらは小さなことですが、積み重なると大きな差になります。
私の場合、とにかく「乾燥時間」をいかに短縮するかをゲームのように楽しんでいます。100円の差は小さく見えますが、月5回利用すれば500円、年間で6,000円の差になります。これらのテクニックは、誰でも簡単に真似できるものばかりです。
1. 自宅で「最強脱水」してから持ち込む
これは「乾燥だけ」を利用する際の最強のテクニックです。自宅の洗濯機で洗濯を済ませた後、脱水だけをもう一度、最も強い設定でかけます。(衣類が傷まないか確認は必要です) 洗濯物が含む物理的な水分量を極限まで減らしてからコインランドリーに持ち込むことで、乾燥時間を確実に10分(100円)単位で短縮できます。これは非常に効果が高いです。
2. 乾燥機が「温まっている」台を選ぶ
コインランドリーに着いたら、まず空いている乾燥機の扉のガラス部分を触ってみます。直前まで誰かが使っていた台は、庫内がまだ温まっています。 冷え切った状態から乾燥をスタートするよりも、すでに温まっている台を使った方が、熱効率が良く、設定温度に達するまでの時間が短縮できるため、その分、乾燥効率が上がり節約につながります。同じ100円でも、乾燥パワーの「実質時間」が変わってくるイメージです。
3. キャッシュレス決済やポイントを活用する
最近のコインランドリーは、現金だけでなく、専用のICカードやスマートフォンアプリでのキャッシュレス決済に対応している店舗が非常に増えています。 こうしたサービスでは、「3,000円チャージで3,300円分使える」といったプレミアム(ポイント還元)が付くことがよくあります。現金で支払うよりも実質的に10%近く安くなるため、頻繁に利用する方は導入しない手はありません。 さらに、スマートフォンのアプリでは、店舗の機械の空き状況を自宅で確認できたり、洗濯終了を通知で知らせてくれたりする機能も付いています。 (参照:例として、AQUA「AQUA Cloud IoTランドリー」など、各社がアプリ決済による利便性とポイント還元を推進しています) この「時間の節約」と「実質割引」の両方を得られるため、使わないのは損と言えるでしょう。
コインランドリーで安く済ませる方法
これまで解説してきた「コインランドリーで安く済ませる方法」を、今日から使える具体的な行動リストとしてまとめます。これらを意識するだけで、あなたのコインランドリー代は確実に安くなります。
安く済ませるための行動リスト
- 基本は「セパレート(別々)」を選ぶ (理由:乾燥時間を自分でコントロールでき、コスト削減の余地が大きいため)
- 洗濯は「自宅」で済ませる(乾燥だけ利用) (理由:コインランドリー代で最も高額なのは洗濯代の場合もあるため。自宅で強めに脱水してから持ち込むのが最強の節約術)
- 乾燥機は「大型」を選ぶ (理由:中型機でパンパンにするより、大型機で余裕を持って回す方が熱効率が良く、結果的に早く乾き、総額が安い場合があるため)
- 「乾いたバスタオル」を1枚投入する (理由:全体の水分をバスタオルが吸い、乾燥時間を短縮できるため)
- 乾燥は「100円ずつ」こまめに追加する (理由:乾燥させすぎの無駄な時間(=無駄な100円)を防ぐため)
- 「温まっている乾燥機」を狙う (理由:スタート時の熱効率を上げ、実質的な乾燥時間を増やすため)
- 「キャッシュレス」を活用する (理由:チャージ時のプレミアムやポイント還元で、実質的な割引を受けるため)
また、料金だけでなく衛生面も重要です。多くの店舗は日々清掃されていますが、利用前には洗濯槽の中や乾燥フィルターの状態を軽くチェックする習慣をつけると良いでしょう。業界団体である「一般社団法人 全国コインランドリー管理業協会」なども、店舗の衛生基準に関する啓発を行っており、清潔な店舗選びの参考になります。
コインランドリー洗濯乾燥別を安く使う総まとめ
「コインランドリー 洗濯 乾燥別 安い」という疑問について、料金比較から具体的な節約術まで詳しく解説してきました。最後に、この記事の最も重要な要点をリスト形式でまとめます。
- コインランドリーで洗濯と乾燥を別々に使うと、一体型より安くなる可能性が高い
- 理由は、乾燥時間を10分(100円)単位で細かく調整できるため
- 洗濯のみの料金相場は容量別(例:10kg 400円)で決まる
- 乾燥のみの料金相場は時間別(例:10分 100円)で決まる
- 別々利用のメリットは「安さ」と「高温ガス乾燥による仕上がりの良さ」
- 別々利用のデメリットは「洗濯物を移し替える手間」と「待ち時間」
- 一体型は「手間がかからない」という利便性が最大のメリット
- 一体型が割高なのは、乾燥効率やコース設定の不柔軟さ、利便性の対価という側面がある
- 洗濯乾燥機が乾かない時は、量を減らす(特に一体型)、フィルター掃除、乾いたタオルを入れるのが有効
- 毛布を洗う際は、洗濯機より一回り大きな乾燥機を選び、途中で裏返すとふんわり仕上がる
- 乾燥機は100円ずつ追加し、乾き具合をこまめに確認するのが最大の節約術
- 直前に使われた「温かい乾燥機」を狙うと熱効率が良い
- 自宅で強めに脱水してから持ち込むと乾燥時間を短縮できる
- キャッシュレス決済のポイント還元を活用すると実質的に安くなる
- 結論:安さ・仕上がり重視なら「別々」、手間・時間重視なら「一体型」を選ぶのが賢い選択
あなたのライフスタイルや洗濯物の量、そして「手間」と「コスト」のどちらを優先するかに合わせて、一体型とセパレート型を賢く使い分けることが、コインランドリーを最も安く、便利に活用する鍵となります。この記事で得た知識を活かし、ぜひ今日から「賢いコインランドリー生活」をスタートさせてください。