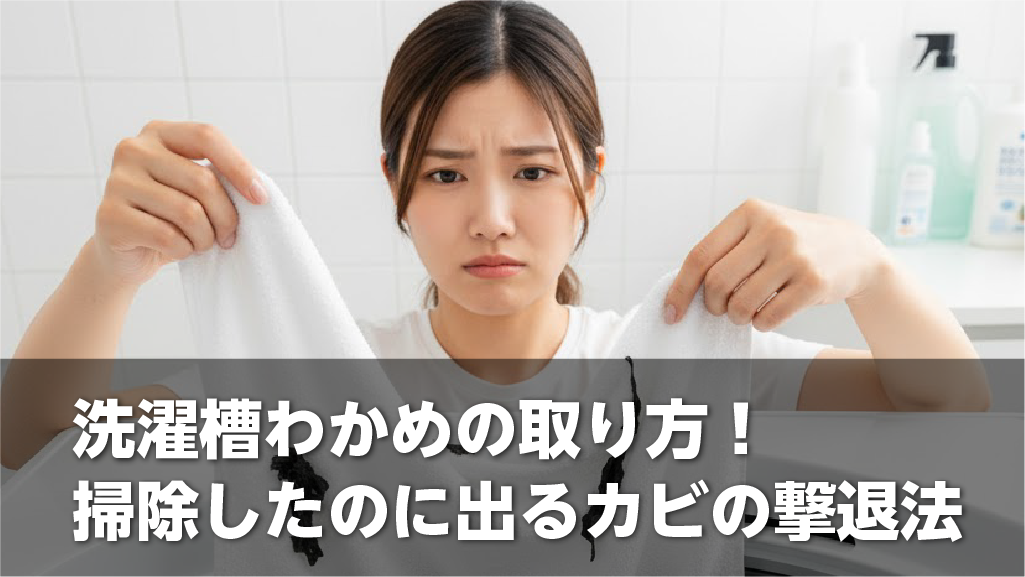お子さんの小学校入学や習字の授業開始を控え、文房具店で習字セットを眺めていると、「洗濯で落ちる墨汁」という便利なアイテムが目に留まりますよね。服を汚して帰ってくる子供の姿を想像すると、「これさえあれば洗濯のストレスが減るかも!」と、つい手を伸ばしたくなるものです。
しかし、その一方で書道教室の先生や経験者の間では「洗濯で落ちる墨汁は使ってはいけない」という声も根強く存在します。なぜ、これほどまでに便利な製品が推奨されないのでしょうか?その背景には、単なる汚れ落ちの良さだけでは測れない、書道という文化が大切にしてきた道具への配慮や、作品の仕上がりへの影響といった、深く、そして重要な理由が隠されています。
この記事では、なぜ洗濯で落ちる墨汁が「使ってはいけない」と言われるのか、その理由を徹底的に深掘りし、あなたの疑問や不安を解消します。普通の墨汁との科学的な成分の違いから、大切な筆が修復不可能なほど痛んでしまうメカニズム、学校現場での実際の扱われ方、そして万が一、どちらの墨汁が服についても慌てないための具体的な落とし方まで、網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、小学生の習字セット選びで後悔しないための、そして本格的な書道の道具を選ぶ上での確かな知識が身につくはずです。
- 洗濯で落ちる墨汁が推奨されない具体的な理由
- 普通の墨汁との成分や性能の決定的な違い
- 大切な筆や作品に与える影響と正しい対処法
- 墨汁が服についた際の状況別の正しい落とし方
洗濯で落ちる墨汁を使ってはいけないと言われる本当の理由

- 洗濯で落ちる墨汁がなぜ推奨されないのか
- 洗濯で落ちる墨汁のデメリットとは?
- 洗濯で落ちる墨汁で筆が痛むって本当?
- 洗濯で落ちる墨汁と普通の墨汁の決定的な違い
- 洗濯で落ちる墨汁を使うと作品が滲む?
- 洗濯で落ちる墨汁は学校で禁止されることも
洗濯で落ちる墨汁がなぜ推奨されないのか
なぜ、あれほど便利な「洗濯で落ちる墨汁」が、書道を学ぶ上で推奨されないのでしょうか。その核心的な理由を先に述べると、「筆の寿命を著しく縮める」「作品の芸術性を損なう」という、書道の世界では看過できない2つの大きな問題点に集約されます。
これは、単に「少し書きにくい」といったレベルの話ではなく、道具の機能を破壊し、作品の価値を根本から揺るがす可能性を秘めているのです。
「洗濯で落ちる」という性能は、科学的に見れば「繊維への定着力が極めて弱い」ことを意味します。衣類に付着しても繊維の奥まで染み込まず、洗剤の力で簡単に剥がれるように設計されているのです。
しかし、この特性が裏目に出ます。本来、墨の粒子を紙の繊維にしっかりと定着させ、永く美しい黒を保つべき書道の世界において、この「定着力の弱さ」は致命的な欠点となります。さらに、洗濯で落ちやすくするために配合された特殊な化学成分が、イタチや馬などの繊細な動物の毛から作られる筆に対して、深刻なダメージを与えてしまうのです。
本質的な問題点
洗濯で落ちる墨汁の問題は、その利便性の代償として、書道が数千年にわたり培ってきた「道具(筆)を大切に扱う文化」と「作品(書)の永続性・芸術性」という根幹を揺るがす点にあるのです。
もちろん、この墨汁が絶対的な悪というわけではありません。汚れを気にせず、子供が文字を書く楽しみに触れる導入としては、非常に優れた製品です。しかし、本格的に書道を学ぶステップに進むのであれば、なぜこれが推奨されないのか、その理由を深く理解しておくことが極めて重要になります。
洗濯で落ちる墨汁のデメリットとは?
洗濯で落ちる墨汁が持つデメリットは、多岐にわたります。ここでは、特に重要となる「筆」「作品」「長期保存性」という3つの観点から、その具体的な問題点を掘り下げていきましょう。
| 観点 | 具体的なデメリット | 詳細な解説 |
|---|---|---|
| 筆への影響 | 筆が内部から固化し、毛が傷む・抜ける | 墨汁に含まれる合成樹脂系の接着剤が、洗浄後も筆の根元(穂首の付け根)に残留します。これが乾燥するとプラスチックのように硬化し、筆のしなやかさを奪います。結果として、毛がゴワゴワになってまとまりを失い、毛先が切れやすくなったり、根元から抜け落ちたりして、高価な筆であってもその寿命を劇的に縮めてしまいます。 |
| 作品への影響 | 墨色に深みがなく、滲みやかすれが不自然になる | 本来の墨が持つ、艶やかで吸い込まれるような「墨色(ぼくしょく)の五彩」と呼ばれる豊かな階調表現が困難です。黒が単調で平面的に見え、作品に立体感や力強さが生まれません。また、界面活性剤の影響で紙質によっては滲みが不自然に広がり、逆に油分が多い紙では墨が弾かれてしまい、美しい「かすれ」の表現も難しくなります。 |
| 長期保存性 | 紫外線や経年による色褪せ(退色)が早い | 日本の国宝級の書物が千年以上もその黒さを保っているのは、主成分の煤(カーボンブラック)が膠の力で紙の繊維に強固に定着しているためです。しかし、定着力の弱い洗濯で落ちる墨汁は、紫外線や空気との接触による酸化に弱く、数年から数十年で黒が薄茶色っぽく色褪せる可能性があります。子供の成長の記録として作品を残したい場合、この点は大きなデメリットです。 |
清書や作品制作には絶対に使用しないでください
これらのデメリットから、コンクールへの出品、学校の課題の清書、命名書など、きれいに仕上げたい、または長く残したいと考えるすべての作品に洗濯で落ちる墨汁を使用することは、専門家の立場から強くお勧めできません。
洗濯で落ちる墨汁で筆が痛むって本当?

はい、これは紛れもない事実です。そして、これが書道の指導者たちが口を揃えて「使ってはいけない」と警鐘を鳴らす最大の理由です。私自身、生徒が使った筆を洗う際に、根元が石のように硬直し、どうやっても元に戻らなくなった経験が何度もあります。その筆は、残念ながらもう使うことはできませんでした。
筆が致命的に傷むメカニズムは、洗濯で落ちる墨汁の接着成分である「合成樹脂(アクリル系エマルジョンなど)」と、普通の墨汁の接着成分である「膠(にかわ)」の性質の違いに起因します。
- 膠(にかわ):動物の皮や骨から作られる天然のコラーゲン(タンパク質)です。水溶性であり、乾いて固まっても、再び水に浸ければ柔らかく溶け出す性質を持っています。そのため、筆の根元に多少残っても、次回の使用時に水に馴染ませる過程で自然にほぐれます。
- 合成樹脂:石油などを原料とする化学合成物質です。水に溶けているように見えますが、水分が蒸発すると樹脂同士が結合して耐水性のある膜を形成します。これは、アクリル絵の具が乾くと水に溶けなくなるのと同じ原理です。
この「乾くと耐水性になる」という性質が、筆にとっては致命的です。筆の毛は、特に根元の部分は密度が高く、洗浄しても墨液が残りやすい場所です。ここに合成樹脂が残留し乾燥すると、毛束が内部から接着されてしまい、カチカチの塊になってしまいます。こうなると、次に水に浸けても樹脂は溶けず、無理にほぐそうとすれば、繊細な毛はいとも簡単に引きちぎれてしまうのです。
筆の手入れは「根元を洗う」のが基本
書道の世界では「筆は根元までおろして、根元まで洗う」のが基本とされています。これは、筆全体の弾力を最大限に活かすためです。しかし、洗濯で落ちる墨汁を使った場合、この基本の手入れがかえって筆の内部に樹脂を残留させ、寿命を縮める原因になりかねないというジレンマを抱えています。
洗濯で落ちる墨汁と普通の墨汁の決定的な違い
見た目は同じ黒い液体ですが、この二つの墨汁は全く異なる目的と成分で作られた「似て非なるもの」です。その決定的な違いは、黒色の元である「煤」を紙に定着させるための「接着剤」と、汚れ落ちを助ける「界面活性剤」の有無にあります。
墨汁の主成分 詳細比較
- 普通の墨汁(伝統的な墨液)
- 着色剤:煤(カーボンブラック)
松や植物油を燃やして採取した炭素の微粒子。粒子が細かく、黒色に深みがあります。
- 接着剤:膠(にかわ)
動物由来の天然たんぱく質。煤を紙の繊維に強力に固着させ、耐水性と長期保存性を与えます。
- その他:水、香料(龍脳など)
膠の腐敗を防ぎ、心を落ち着かせる効果のある香料が微量に加えられています。
- 着色剤:煤(カーボンブラック)
- 普通の墨汁(伝統的な墨液)
- 洗濯で落ちる墨汁
- 着色剤:煤(カーボンブラック)
普通の墨汁と同じく煤が使われることが多いですが、落としやすくするために表面加工されている場合もあります。
- 接着剤:合成樹脂(アクリル系など)
水分が蒸発すると固まる化学合成の接着剤。膠に比べて定着力が弱く、耐水性も低く設計されています。
- 添加剤:界面活性剤
洗剤の主成分。衣類の繊維と墨の粒子の間に浸透し、汚れを浮き上がらせて落としやすくします。これが滲みの原因にもなります。
- 着色剤:煤(カーボンブラック)
このように、普通の墨汁が「いかに紙に強く定着させるか」を追求して作られているのに対し、洗濯で落ちる墨汁は「いかに繊維から簡単に剥がせるか」という正反対の目的で作られています。文具メーカーの呉竹の公式サイトなどでも、書道用の墨液は用途別に様々な種類が紹介されており、その成分や特性の違いが詳しく解説されています。
洗濯で落ちる墨汁を使うと作品が滲む?
はい、普通の墨汁に比べて格段に滲みやすい傾向があります。これも、汚れを落としやすくするために配合されている「界面活性剤」が大きく影響しています。
水の分子は、本来お互いを引きつけ合う「表面張力」という力を持っています。この力があるため、水は玉のような形を保とうとします。普通の墨汁は、この水の性質を活かして、書いた線の輪郭をくっきりと保つことができます。
しかし、界面活性剤には、この表面張力を弱める働きがあります。コップの水に洗剤を一滴垂らすと、水がフワッと広がるのと同じ現象です。この状態で文字を書くと、墨汁が紙の繊維に触れた瞬間、本来留まるべき範囲を超えて、毛細管現象によってじわじわと繊維の隙間に染み渡ってしまうのです。これが「滲み」の正体です。
私の場合、生徒に線の太さをコントロールする練習をしてもらう際には、滲みの少ない墨汁を必ず選ぶようにしています。意図しない滲みは、自分の筆遣いが原因なのか、墨汁の性質が原因なのかが分からなくなり、上達の妨げになってしまうからです。「トメ」がしっかり止まらず、「ハライ」の先がぼやけてしまうのは、初心者にとって大きなストレスになります。
特に、学校で配布されることの多い吸水性の高い半紙では、この滲みが顕著に現れます。せっかく練習して上手に書けるようになっても、清書で文字が滲んで台無しになってしまったら、お子さんのやる気も削がれてしまいますよね。
洗濯で落ちる墨汁は学校で禁止されることも
「セットに最初から入っていたから」「近所の文房具店で勧められたから」という理由で洗濯で落ちる墨汁を用意したところ、学校の最初の授業で「この墨汁は使わないでください」と指導され、慌てて買い直すことになった、という話は決して珍しくありません。
学校や書道教室が洗濯で落ちる墨汁を推奨しない、あるいは禁止する背景には、主に以下のような教育的な配慮があります。
学校が洗濯で落ちる墨汁を推奨しない理由
- 道具を大切に扱う心を育むため
「汚したら大変だから、丁寧に墨をする」「使い終わったら、筆や硯をきれいに洗う」といった一連の作業を通じて、道具への愛着や物を大切にする心を育むことを、書写教育の重要な目的の一つと捉えています。利便性だけを追求することは、この学習機会を奪うことになりかねません。 - 伝統文化としての書道を教えるため
日本の書道は、墨の濃淡や滲み、かすれといった要素も作品の美しさとされています。本来の墨の性質を体験させ、その奥深さに触れさせることが、伝統文化の継承に繋がると考えているためです。 - 公正な評価を行うため
普通の墨汁を使っている児童と、洗濯で落ちる墨汁を使っている児童では、作品の仕上がりの見た目(墨色や滲み)が異なります。全員を同じ基準で公正に評価するため、使用する道具を統一したいという意図もあります。
もちろん、全ての学校で禁止されているわけではなく、低学年の導入期や、準備・片付けの時間を短縮したいという現実的な理由から、練習用に限って使用を許可している学校も増えています。重要なのは、自己判断で購入する前に、必ず学校から配布される「学用品一覧」の注意書きをよく読んだり、担任の先生に直接確認したりすることです。事前の確認一手間で、無駄な出費や親子での気まずい思いを避けることができます。
後悔しないために!洗濯で落ちる墨汁との正しい付き合い方

- 洗濯で落ちる墨汁が固まる原因と対策
- 洗濯で落ちる墨汁の正しい落とし方
- 普通の墨汁が服についた時の落とし方
- 小学生の習字セットでおすすめの選び方
- 本格的な書道の道具の選び方
- まとめ:洗濯で落ちる墨汁を使ってはいけない場面を理解しよう
洗濯で落ちる墨汁が固まる原因と対策
前述の通り、洗濯で落ちる墨汁は、主成分である合成樹脂の性質上、普通の墨汁よりも硯の上で固まりやすいという弱点があります。特に、エアコンの風が当たる場所や乾燥した室内では、あっという間に表面に膜が張り、ダマになってしまいます。
この「固化」を防ぎ、墨汁を最後まで快適に使うためには、いくつかの対策を徹底することが重要です。
墨汁を固まらせないための具体的な対策
- 少量ずつ出すことを徹底する
硯の「陸(おか)」と呼ばれる平らな部分に、まずは少量だけ墨汁を出します。そして、書いている途中でかすれてきたら、その都度こまめに注ぎ足すようにしましょう。一度にたくさん出すと、空気に触れる面積が広くなり、乾燥が早まってしまいます。 - 短時間でも乾燥から守る
お手本を変える、電話に出るなど、ほんの数分間、筆を置く場合でも油断は禁物です。硯の上に、濡らして軽く絞った小さな布やティッシュを被せておくだけで、水分の蒸発を大幅に防ぐことができます。サランラップをかけておくのも非常に効果的です。 - 使い終わったら「すぐに」「完全に」洗浄する
練習が終わったら、硯に残った墨汁は放置せず、すぐに洗い流してください。ティッシュや柔らかい布で残った墨液を吸い取ってから、流水で優しく洗い流します。この時、硬いタワシなどでこすると硯の表面(鋒鋩・ほうぼう)を傷つけてしまうので、必ず指の腹や柔らかいスポンジで洗いましょう。
これらの対策は、一見すると面倒に感じるかもしれません。しかし、このひと手間が道具を長持ちさせ、結果的に経済的な負担を減らすことに繋がります。正しい道具の扱い方を身につけることも、書道の大切な学習の一部です。
洗濯で落ちる墨汁の正しい落とし方
「洗濯で落ちる」という名前が付いていますが、それはあくまで「普通の墨汁に比べて落ちやすい」という意味であり、どんな状況でも100%きれいに落ちることを保証するものではありません。特に、時間が経過して汚れが乾いてしまったり、生地の素材によっては、シミが残ってしまうことも十分にあり得ます。
もし服に付けてしまった場合は、「スピード」と「正しい手順」が何よりも重要です。慌てて間違った対処をすると、かえって汚れを広げてしまうので注意しましょう。
洗濯で落ちる墨汁のステップ別・落とし方ガイド
- 【応急処置】乾く前に、すぐにつまみ取る
墨汁が付いたら、絶対にこすらず、乾いたティッシュや布を押し当てて、できるだけ多くの墨液を吸い取ります。その後、汚れた部分の下に乾いた布を当て、水を少し含ませた別の布で、汚れの周囲から中心に向かって優しく叩き(つまみ洗い)、下の布に汚れを移し取ります。 - 【予洗い】固形石鹸で直接もみ洗い
帰宅後、すぐに洗濯機に入れるのではなく、まずは汚れた部分をぬるま湯で濡らし、洗濯用の固形石鹸(泥汚れ用などが効果的)を直接塗り込みます。そして、生地を傷めないように注意しながら、指の腹で優しくもみ洗いをしてください。石鹸のアルカリ成分が、墨の粒子を分解するのを助けます。 - 【つけ置き】酸素系漂白剤で最終手段
もみ洗いをしても黒ずみが残っている場合は、洗面器などに40~50℃のお湯を張り、規定量の「酸素系」粉末漂白剤をよく溶かします。そこに衣類を入れ、30分から1時間ほどつけ置きしてください。 - 【本洗い】他の洗濯物と一緒に洗濯機へ
つけ置きが終わったら、液ごと洗濯機に入れ、普段通りに洗濯用洗剤を加えて洗濯します。
絶対にやってはいけないこと
色柄物に「塩素系」漂白剤(ハイターなど)を使うと、その部分だけ色が抜けてしまい、修復不可能になります。必ず「酸素系」(ワイドハイターなど)を使用し、洗濯表示をしっかり確認してください。
普通の墨汁が服についた時の落とし方

一方、膠で強力に固着する「普通の墨汁」が付いてしまった場合、残念ながら家庭での洗濯で完全に落とすことは極めて困難です。膠が乾燥して耐水性を持つと、煤の粒子が繊維の奥にガッチリと固定されてしまうため、通常の洗剤では歯が立ちません。
しかし、付いてすぐの応急処置として、古くから伝わるいくつかの方法を試す価値はあります。
代表的なのは、「ご飯粒」や「歯磨き粉」を利用する方法です。これは、ご飯粒のでんぷんが持つ粘着力や、歯磨き粉に含まれる研磨剤の物理的な力で、繊維に絡みついた煤の粒子をかき出すことを狙った民間療法です。
応急処置の手順
- 墨が付いた部分にご飯粒(炊いたもの)を置き、指で押し付けるように練り込みます。ご飯粒が墨を吸って黒くなったら、新しいものに取り替えて、汚れが薄くなるまで繰り返します。
- その後、固形石鹸や部分洗い用の洗剤を付けて、優しくもみ洗いをします。
なぜこの方法が有効とされるのか?
でんぷんの粘り気が、繊維の奥に入り込んだ微細なカーボン粒子を吸着し、引き離す効果があると考えられています。ただし、これはあくまで化学的な裏付けが完全ではない民間療法であり、生地を傷めるリスクも伴います。デリケートな素材や大切な衣類には試さないでください。
私であれば、お気に入りの服に普通の墨汁が付いてしまった場合は、下手に自分で対処しようとせず、その足で信頼できるクリーニング店に直行します。その際、「付いたのは普通の書道用の墨汁で、付いてから〇時間経っています」と具体的な情報を伝えることで、プロが最適なシミ抜き方法を選択しやすくなり、きれいに落ちる確率も高まります。
小学生の習字セットでおすすめの選び方
これまでの情報を総合すると、小学生のお子さんのための習字セット選びでは、単にデザインや価格だけで決めるべきではないことがお分かりいただけたかと思います。長く、そして快適に使うための、後悔しない選び方のポイントを具体的にご紹介します。
小学生の習字セット選び 3つのチェックポイント
- 【最優先】学校の方針を必ず確認する
購入前に、学校から配布された資料を隅々まで確認し、墨汁の種類(「洗濯で落ちるタイプは不可」など)や、道具に関する指定がないかをチェックします。不明な点があれば、遠慮なく学校や担任の先生に問い合わせましょう。 - 【品質重視】セットの中でも「筆」は妥協しない
バッグや硯、文鎮などはセット品で十分ですが、「筆」だけは上達を大きく左右します。良い筆の条件は「穂先がシャープに尖っている」「根元がしっかりしていて弾力がある」「毛がバラバラにならず、まとまりが良い」の3点です。可能であれば、セットとは別に、書道用品店で1,000円~2,000円程度の学童用筆を一本買い足してあげることを強くお勧めします。 - 【実践的】墨汁は「使い分け」も視野に入れる
もし学校の許可があり、汚れが特に心配な低学年のうちは、「家での練習や宿題は洗濯で落ちる墨汁」「学校への提出物や清書は普通の墨汁」というように、2種類を使い分けるのも非常に賢い方法です。これにより、洗濯の負担を減らしつつ、本番ではしっかりとした作品作りができるようになります。
最近では、バッグと基本的な道具(硯、文鎮など)だけがセットになっており、筆や墨汁は別売りで好きなものを選べる商品も増えています。お子さんのやる気を引き出すためにも、一緒に文房具店へ行き、本人が気に入ったデザインのバッグを選ばせてあげながら、中身の品質は親がしっかりとチェックしてあげるのが理想的な選び方と言えるでしょう。
本格的な書道の道具の選び方
もしお子さんが書道に深い興味を示したり、ご自身が趣味として本格的に始めてみたいと思ったりしたなら、道具選びは書道の大きな楽しみの一つとなります。「書は文房四宝(ぶんぼうしほう)に始まる」と言われるように、良い道具はあなたの上達を力強くサポートしてくれます。
ここでは、基本的な「筆・墨・硯・紙」の選び方をご紹介します。
- 墨(Sumi Ink):
最初は、膠系の良質な液体墨(墨汁)から始めるのが手軽でおすすめです。書道用品店で「清書用」「作品用」と表示されているものを選ぶと良いでしょう。いずれは、ぜひ固形墨に挑戦してみてください。硯でゆっくりと墨をする時間は、心を落ち着かせ、精神を集中させるための大切な儀式です。墨の香りや、する感触、墨色の変化など、五感で書道の世界を味わうことができます。 - 硯(Suzuri / Inkstone):
墨をすりおろすための硯は、墨の発色を左右する重要な道具です。安価なセラミック製やプラスチック製のものもありますが、できれば天然石で作られた「石硯(せきけん)」を選びましょう。石硯の表面には「鋒鋩(ほうぼう)」と呼ばれる微細な凹凸があり、これがヤスリの役割を果たして、きめ細やかで伸びの良い墨液を作ってくれます。 - 筆(Fude / Brush):
筆は、書く文字の大きさや書体によって、また、表現したい線の種類によって無数の種類が存在します。初心者が最初に一本選ぶなら、馬やイタチなどの硬い毛と、羊などの柔らかい毛を混ぜて作られた「兼毫筆(けんごうふで)」が、弾力と含みのバランスが良く、扱いやすいのでおすすめです。 - 紙(Kami / Paper):
書道で使う紙は、一般的に「半紙(はんし)」と呼ばれます。同じ半紙でも、製造方法によって滲みやすいもの、かすれが出やすいものなど、驚くほど個性があります。色々試してみるのが一番ですが、最初は「滲みが少ない」あるいは「手漉き(てすき)」と書かれたものを選ぶと、筆の運びをコントロールしやすく、練習に適しています。
これらの本格的な道具は、ぜひ書道用品の専門店に足を運び、知識豊富な店員さんに相談しながら選んでみてください。インターネットでも購入できますが、実際に手に取って重さや感触を確かめることで、道具への愛着も一層深まるはずです。
まとめ:洗濯で落ちる墨汁を使ってはいけない場面を理解しよう

今回は、「洗濯で落ちる墨汁を使ってはいけない」と言われる理由について、その背景から具体的な対処法まで、詳しく解説してきました。便利な製品ではありますが、その特性を正しく理解し、TPOに合わせて使い分けることが何よりも大切です。最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認しておきましょう。
- 洗濯で落ちる墨汁を使ってはいけないと言われる主な理由は筆へのダメージと作品の質の低下
- デメリットは筆が固まりやすい、墨色に深みが出ない、長期保存に向かない点
- 筆が痛む原因は墨汁に含まれる合成樹脂成分が乾燥後に硬化するため
- 普通の墨汁との違いは接着剤の成分(膠 vs 合成樹脂)と界面活性剤の有無
- 洗濯で落ちる墨汁は界面活性剤の影響で作品が滲みやすいことがある
- 学校によっては教育方針から使用が禁止されている場合もあるため事前の確認が重要
- 洗濯で落ちる墨汁は水分が蒸発しやすいため硯の上で固まることがある
- 固まりを防ぐにはこまめに使い、使用後はすぐに硯を洗うことが大切
- 洗濯で落ちる墨汁でも服に付いたらすぐに水洗いと石鹸でのもみ洗いが効果的
- 時間が経った汚れには酸素系漂白剤でのつけ置きを試す
- 普通の墨汁が服についた場合は家庭で落とすのは困難
- 応急処置としてご飯粒や歯磨き粉を使う方法があるがクリーニング店への相談が最善
- 小学生の習字セットは学校の方針を確認し、筆の質を重視して選ぶのがおすすめ
- 練習用と清書用で墨汁を使い分けるのも有効な方法
- 本格的な書道を始めるなら専門店で相談しながら道具を選ぶのが確実