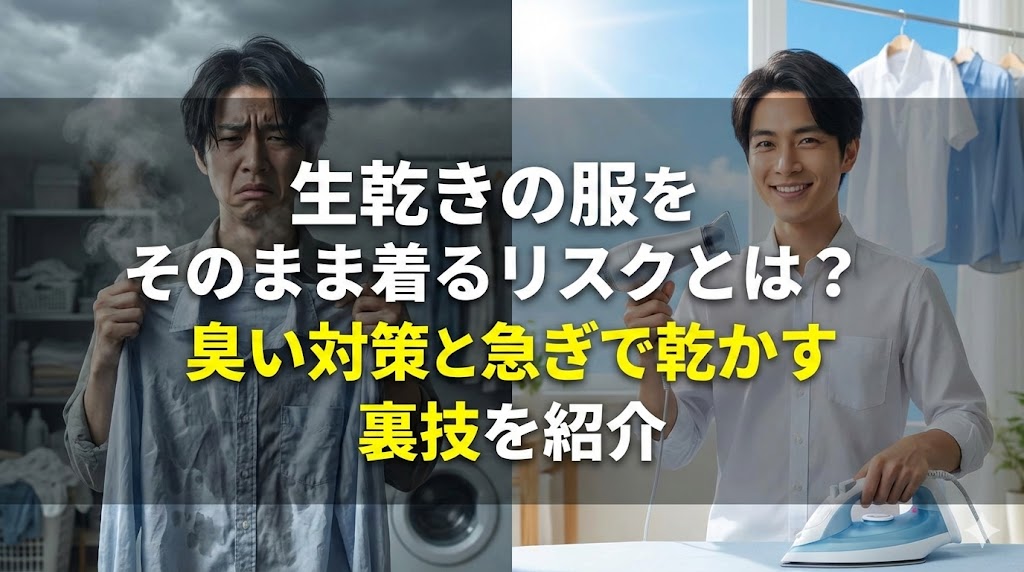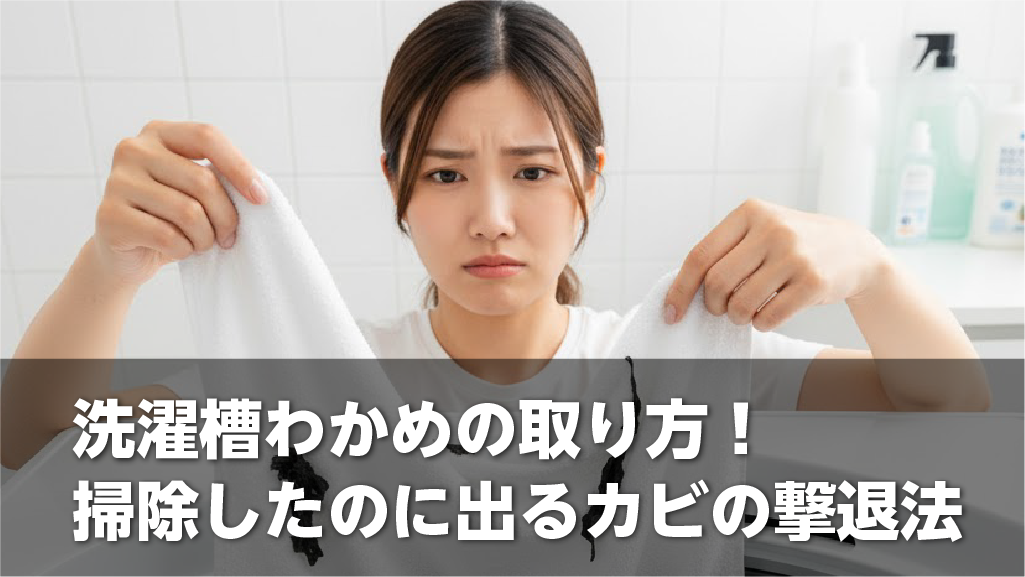
※この記事にはプロモーションが含まれています。
洗濯を終え、清潔になったはずの衣類を取り出そうとした瞬間、黒いヒラヒラとした「わかめ」のようなものが付着していて、思わずため息が出た…そんな経験はありませんか。そのわかめの正体は、洗濯槽の裏側に潜む黒カビや、それが洗剤カス・皮脂汚れと混ざり合って固まった汚れの塊です。せっかく洗濯したのに、これでは衣類がキレイになったとは言えません。
「この間、洗濯槽を掃除したのにわかめが出る…」とお悩みの方も多いでしょう。それは、一度の掃除では落としきれないほど、汚れが根深く蓄積しているサインかもしれません。このわかめの本当の原因を理解し、ご家庭の洗濯機(縦型やドラム式)に合った正しい洗濯槽のわかめの取り方を実践しなければ、悩みは永遠に解決しない可能性があります。
この記事では、なぜわかめが発生するのかという根本的な原因から、塩素系クリーナーや酸素系クリーナー、オキシクリーンの特性と使い方、しつこいわかめが服についた時の取れない場合の対処法まで、徹底的に解説します。
さらに、酸素系クリーナー使用時に必須となるわかめをネットですくう時のすくい方、見落としがちな排水フィルターの掃除、そして二度とわかめを発生させないための効果的な予防策、つかないようにする方法も詳しくご紹介します。正しい知識で、あの不快なわかめに別れを告げましょう。
- 洗濯槽から出るわかめの正体とその根本的な原因
- 塩素系・酸素系・オキシクリーンを使った具体的な掃除方法とその違い
- ドラム式と縦型洗濯機、それぞれに適したわかめ対策のポイント
- わかめの発生を未然に防ぐための効果的かつ簡単な予防策
洗濯槽わかめの正体と基本的な取り方

- 洗濯槽から出るわかめの原因とは?
- 洗濯槽わかめは縦型で出やすい?
- まず試したい簡単な洗濯槽わかめの取り方
- 洗濯槽わかめが服についた時の取れない対処法
- 洗濯槽わかめをネットですくう時のすくい方
洗濯槽から出るわかめの原因とは?
洗濯機から出てくる、あの黒くヒラヒラとした「わかめ」の正体。それは、洗濯槽の裏側にびっしりと繁殖した黒カビです。しかし、単なるカビだけではありません。実際には、溶け残った洗剤カス、柔軟剤の残留成分、衣類から出た皮脂汚れ、アカ、そして空気中のホコリなどが混ざり合い、ミルフィーユのように層状に蓄積したものです。
洗濯槽の裏側は、私たちの目には見えませんが、カビにとってこれ以上ないほど理想的な環境が揃っています。
カビが繁殖する3大条件
- 湿度(水分): 洗濯槽は常に水を使う場所であり、特に洗濯直後は湿度90%を超えることも。洗濯機のフタを閉めっぱなしにすると、内部の水分が蒸発せず、高湿度が維持されてしまいます。
- 栄養分: カビはあらゆる有機物を栄養源にします。溶け残った洗剤カスや柔軟剤、人間の皮脂やアカ、衣類の繊維クズは、カビにとってごちそうの山です。
- 温度: カビは20℃~30℃の温度で最も活発に繁殖します。お風呂の残り湯を使った洗濯や、梅雨時・夏場の気温は、まさにカビの活動を促進させてしまいます。
これらの条件が完璧に揃った洗濯槽の裏側で、カビや汚れが何層にもわたって蓄積していきます。そして、その蓄積した汚れが洗濯槽クリーナーによる掃除や、日々の洗濯時の強い水流によって「剥がれ落ちた」もの、それが「わかめ」の正体なのです。
つまり、わかめが洗濯槽内や衣類に現れたということは、「洗濯槽の裏側が、すでに取り返しのつかないレベルで汚染されている」という危険信号に他なりません。
洗濯槽わかめは縦型で出やすい?

「うちはドラム式だから大丈夫」「縦型はカビやすいと聞く」といった話を耳にすることがありますが、これは洗濯機の構造的な違いに起因しています。結論から言うと、ドラム式洗濯機よりも縦型洗濯機の方が、構造的にわかめ(黒カビ)が発生しやすい傾向にあります。
その最大の理由は、洗濯槽の構造と使用する水の量にあります。
縦型洗濯機がカビやすい理由:
縦型洗濯機は、衣類を洗うための穴が開いた「洗濯槽(内槽)」と、その外側で水を受け止める「外槽」の二重構造になっています。洗濯時には、この内槽と外槽の隙間に大量の水を溜めて水流で洗います。この「隙間」こそが問題で、常に湿気がこもりやすく、洗剤カスや汚れがヘドロのように溜まりやすい「カビの巣窟」となるのです。わかめもこの隙間で大量に培養されます。
ドラム式洗濯機の特徴:
一方、ドラム式洗濯機は、ドラム(内槽)が横や斜めを向いており、衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が基本です。縦型に比べて非常に少ない水量で洗濯できる(節水)のが特徴です。そのため、縦型のような「水の溜まる広大な隙間」が構造的に少ないと言えます。
さらに、ドラム式洗濯機の多くは「乾燥機能」を標準搭載しています。洗濯後に乾燥機能(ヒートポンプ式やヒーター式)を頻繁に使うことで、洗濯槽全体が高温で強制的に乾燥されます。この高温・乾燥状態が、湿気を好む黒カビの繁殖を強力に抑制する効果をもたらします。
ドラム式でも油断は禁物!
「ドラム式だからカビない」というわけでは決してありません。ドラム式特有の注意点として、「ドア(フタ)のゴムパッキン」が挙げられます。このパッキンの溝には水が残りやすく、髪の毛や糸くずが溜まりがちです。ここを清掃せずに放置すると、パッキン自体が黒カビだらけになり、それが衣類に付着したり、ニオイの原因になったりします。
また、節水であるがゆえに、洗剤を入れすぎるとすすぎが不十分になり、結果として洗剤カスが残りやすいという側面もあります。
まず試したい簡単な洗濯槽わかめの取り方
洗濯槽にわかめが浮いているのを発見したら、あるいは洗濯物に付着し始めたら、すぐに洗濯槽の掃除を実行する必要があります。わかめの取り方として最も簡単で基本的な方法は、市販の「洗濯槽クリーナー」を使用することです。
洗濯槽クリーナーには大きく分けて「塩素系」と「酸素系」の2種類があり、それぞれ得意分野が異なります。どちらもドラッグストアやホームセンターで手軽に入手可能です。
1. 塩素系クリーナーを使った取り方(カビを「溶かす」)
塩素系クリーナーの主成分は「次亜塩素酸ナトリウム」です。これはキッチン用の漂白剤などにも使われる成分で、非常に強力な殺菌力と分解力を持ちます。カビの菌糸の根元から化学的に分解し、汚れごと「溶かし」て除去するのが最大の特徴です。
【塩素系クリーナーの手順】
- 槽内を空にする: 洗濯物が残っていないことを確認します。(※衣類を入れたまま使うと、強力な漂白作用で脱色・変色します)
- 電源を入れ、給水する: 洗濯機の電源を入れ、「槽洗浄コース」を選択します。もし槽洗浄コースがなければ、「標準コース」を選び、高水位(一番上の水位)に設定します。
- クリーナーを投入する: 液体タイプのクリーナーを1本全て、洗濯槽に直接投入します。
- 運転を開始する: スタートボタンを押し、槽洗浄コース(または標準コース1サイクル:洗い→すすぎ→脱水)を最後まで運転させます。つけ置きは基本的に不要です。(※製品や洗濯機の指示に従ってください)
- 終了後、乾燥させる: 運転が終了したら、フタを開けて洗濯槽の内部をしっかりと乾燥させます。
塩素系のメリットは、汚れを溶かすため、掃除後にわかめが浮いてくることが少なく、すくい取る手間がかからない点です。また、冷水でも十分な効果を発揮します。
塩素系クリーナー使用時の最重要注意点
塩素系クリーナーは、特有のツンとした刺激臭(プールの消毒のようなニオイ)があります。使用中は必ず窓を開ける、換気扇を回すなど、十分な換気を行ってください。気分が悪くなる可能性があります。また、皮膚に直接触れたり、目に入ったりしないよう、ゴム手袋や保護メガネの使用も推奨されます。
2. 酸素系クリーナーを使った取り方(汚れを「剥がす」)
酸素系クリーナーの主成分は「過炭酸ナトリウム」です。(オキシクリーンなどもこの一種です)。こちらは、お湯と反応することで強力な発泡力を発揮し、その泡の力で洗濯槽の裏側にこびりついた汚れを物理的に「剥がし取る」のが特徴です。
【酸素系クリーナーの手順】
- 槽内を空にする: 洗濯物が残っていないことを確認します。
- 高水位まで「お湯」を溜める: ここが最重要ポイントです。酸素系クリーナーは、40℃~50℃のお湯で最も効果を発揮します。給湯器から直接お湯を溜めるか、お風呂の残り湯(ただし入浴剤入りは避ける)を活用します。水では効果が激減します。
- クリーナーを投入し、撹拌する: 規定量の酸素系クリーナー(粉末)を投入し、「洗い」モードで5分~10分ほど運転させ、クリーナーをしっかり溶かします。
- 「つけ置き」する: 運転を一時停止し、そのまま2時間~6時間ほど放置(つけ置き)します。(※一晩中など、長すぎる放置は洗濯槽の部品を傷める可能性があるため、製品の指示時間を守ってください)
- わかめをすくい取る: つけ置き後、水面に浮いてきた大量のわかめ(汚れ)を、ゴミ取りネットなどで丁寧にすくい取ります。(詳細は次項)
- 運転を再開する: わかめをある程度すくい取ったら、標準コースで1~2サイクル運転し、残った汚れを洗い流します。
- 終了後、乾燥させる: 運転終了後、フタを開けて内部を乾燥させます。
酸素系は、ニオイが穏やかで、取れた汚れが目に見えるため達成感がありますが、「お湯の準備」と「わかめをすくう手間」がかかるのが大きな特徴です。
私の場合、初めての掃除や徹底的にやりたい時は手間を惜しまず酸素系を、時間が無い時や定期メンテナンスには手軽な塩素系を、と使い分けています。
洗濯槽わかめが服についた時の取れない対処法
洗濯が終わったばかりの白いTシャツやタオルに、黒いわかめが点々と…。これほどがっかりすることはありません。特に、そのまま乾燥機にかけてしまうと、熱で汚れが固着してますます取れにくくなるため、乾燥前に必ず対処が必要です。

もし洗濯槽わかめが服についてしまった場合、それは「カビと汚れの塊」が付着している状態です。以下のステップで冷静に対処してください。
ステップ1:物理的に取り除く(乾いた状態で)
まず、衣類が濡れている状態でもみ洗いしたり、擦ったりしないでください。汚れが繊維の奥に入り込んでしまいます。
できれば一度乾かすか、濡れた状態でも、まずはベランダや屋外など汚れても良い場所で、衣類をバサバサと強く振ります。表面に軽く付着しているわかめは、これである程度払い落とすことができます。
乾いた後であれば、粘着テープ(衣類用のコロコロ)を使って優しく表面のわかめを取り除くのも有効です。ただし、強く押し付けると繊維に入り込むので注意してください。
ステップ2:つけ置き洗い(酸素系漂白剤が必須)
物理的に取り除けなかったり、繊維に染み込むように付着してしまったりした「取れない」わかめには、酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウムが主成分の粉末タイプが最も効果的)を使ったつけ置き洗いが非常に有効です。
- 洗面器やバケツ、タライを用意します。
- 40℃~50℃のお湯を張り、そこに酸素系漂白剤を規定量(製品の指示に従ってください)溶かします。
- わかめが付着した衣類を、その漂白液にしっかりと沈めます。
- そのまま30分~1時間ほどつけ置きします。汚れがひどい場合は2時間程度まで延長しても構いません。
- 時間が経ったら、衣類を取り出し、わかめが付着していた部分を軽くもみ洗いします。多くの場合、この時点で汚れがふやけてポロポロと取れてきます。
- 最後に、洗濯機で通常の洗濯(すすぎ・脱水)を行い、しっかりと乾かします。
注意点:塩素系漂白剤(ハイターなど)は絶対に使わないで!
「カビだから」という理由で、塩素系漂白剤(キッチンハイターや衣類用ハイターなど)を使おうと考えるかもしれませんが、これはNGです。
塩素系漂白剤は色柄物の衣類の色を完全に落としてしまいます(脱色)。白い衣類であっても、生地の繊維(特にポリウレタンなど)を傷め、黄ばみや劣化の原因になることがあります。
服についたわかめを落とすのが目的ですので、まずは色柄物にも安全に使える酸素系漂白剤から試すのが鉄則です。
この対処法は、あくまで「服についてしまった汚れ」を取り除くための応急処置です。根本的な原因である洗濯槽が汚れたままでは、次回の洗濯で再び同じ悲劇が繰り返されます。衣類の処置が完了したら、間を置かずに必ず洗濯槽本体の掃除を実行してください。
洗濯槽わかめをネットですくう時のすくい方
酸素系クリーナー(オキシクリーンなど)を使って洗濯槽を掃除すると、つけ置き後、水面に「閲覧注意」レベルの大量のわかめ(黒カビやヘドロ汚れ)が浮かんできます。
この浮かんできたわかめを、「そのまま排水してしまえば楽だ」と考えてはいけません。この作業を怠ると、大量の汚れが排水ホースや排水口に詰まり、深刻な排水エラーや水漏れの原因になる可能性があります。また、排水しきれなかったわかめが洗濯槽の底に残り、結局、掃除後のすすぎ運転で何度も浮き上がってきて、キリがなくなってしまいます。
そのため、酸素系クリーナーを使った場合は、「排水前に、浮いているわかめを物理的にできる限りすくい取る」という作業が絶対に必要です。
【わかめすくいに最適な道具】
わかめを効率的にすくうためには、目が細かく、水だけを通すネットが最適です。
- お風呂の湯垢取りネット: 100円ショップなどで手軽に入手できます。お風呂の湯面に浮いた髪の毛やゴミを取るためのもので、この作業に最適です。
- 金魚・熱帯魚用のネット(アクアリウムネット): これも目が細かく、柄が長いため使いやすいです。
- 即席DIYネット(針金ハンガー + 古ストッキング): コストをかけたくない場合、クリーニング店でもらうような針金ハンガーをひし形や円形に引き伸ばし、伝線した古いストッキングを被せれば、高性能なゴミすくいネットが完成します。ストッキングの目の細かさは、小さなわかめもしっかりキャッチしてくれます。
- 料理用のあく取り網: 代用できますが、目が粗いと小さなわかめを取り逃します。また、衛生面を考慮し、必ず掃除専用として使い分けてください。
【上手なすくい方のコツ】
わかめは水面に浮いているものだけでなく、水中に漂っていたり、底に沈んでいたりするものも多いです。 そこで、一時停止している状態から、「洗い」モードのボタンを押し、数秒だけ洗濯槽を回転させて(撹拌して)すぐに「一時停止」します。
この水流によって、底に沈んでいたわかめが再び水面に舞い上がってきます。水面が落ち着き、わかめが集まってきたところを、用意したネットで根こそぎすくい取ります。これを、すくい取れるわかめがほとんどなくなるまで、3~5回ほど繰り返します。
この作業は、酸素系クリーナーでの掃除において最も時間と手間がかかる部分ですが、ここを丁寧に行うことで、掃除後の仕上がりが格段に良くなり、排水詰まりのリスクも回避できます。
掃除しても出る?しつこいカビ対策と予防法

- 洗濯槽わかめが掃除したのに出る理由
- 洗濯槽わかめの掃除 塩素系と酸素系の違い
- 洗濯槽わかめの掃除にオキシクリーンは有効か
- ドラム式洗濯槽わかめの特有な取り方
- 排水フィルター掃除も洗濯槽わかめ対策に重要
- 洗濯槽わかめを予防しつかないようにする方法
- まとめ:正しい洗濯槽わかめの取り方で清潔に
洗濯槽わかめが掃除したのに出る理由
「この間、丸一日かけて洗濯槽クリーナーで掃除したばかりなのに、また黒いわかめが出てきた…」これは非常によくある悩みであり、多くの人がここで挫折してしまいます。
洗濯槽わかめが掃除したのにすぐに出てくる主な理由は、「一度の掃除では取りきれないほど、カビや汚れが頑固に、そして分厚く蓄積している」からです。
長年掃除をしていなかった洗濯槽の裏側は、カビや洗剤カスがミルフィーユのように何層にも重なっています。市販のクリーナー(特に酸素系)を使用すると、その強力な発泡力で表面の汚れの層を剥がし取ります。しかし、一度の掃除で全ての層を剥がしきることは難しく、中途半端に剥がれかかった汚れの層が残ってしまうのです。
そして、掃除後の通常洗濯の際に、その「剥がれかけ」のわかめが水流によって少しずつ剥がれ落ち、洗濯物に付着してしまうのです。これが「掃除したのに出る」の正体です。
その他にも、以下のような原因が考えられます。
- クリーナーの洗浄力不足: 蓄積した汚れのレベルに対して、使用したクリーナーの洗浄力が単純に不足しているケース。安価なクリーナーでは太刀打ちできない場合があります。
- クリーナーの使用方法の間違い: 最も多いのが、酸素系クリーナーを使用する際に「水」で掃除してしまったケースです。前述の通り、酸素系は40℃~50℃のお湯でなければ効果が半減します。また、塩素系でもつけ置き時間が短すぎる(または長すぎる)と効果が出ません。
- 見落としがちな場所の汚れ: 洗濯槽の裏側だけでなく、洗剤投入ケース、柔軟剤投入口、フタの裏側、糸くずフィルター(排水フィルター)といった周辺部品にカビが残っていると、そこが新たな発生源となり、槽内にカビの胞子をまき散らしている可能性があります。
【対策】メーカー純正クリーナーを試す価値あり
私自身、市販のクリーナー(塩素系・酸素系ともに)を何度も試してもわかめが出続けた経験があります。その時、最終手段として試したのが、洗濯機メーカー(日立やパナソニックなど)が販売している「純正の洗濯槽クリーナー」でした。
例えば、日立の「SK-1500」やパナソニックの「N-W1A(縦型用)」「N-W2(ドラム式用)」などは、市販品よりも高価(2,000円前後)ですが、その分、大容量(1500mlなど)で成分濃度も強力とされています。これらを使い、洗濯機の説明書に記載されている公式の「槽洗浄コース」(多くの場合11時間など長時間)で運転したところ、あれほどしつこかったわかめがピタリと出なくなりました。
市販品で解決しない場合は、最後の砦として、ご自宅の洗濯機メーカーの純正クリーナーを試してみることを強く推奨します。家電量販店やメーカーの公式オンラインストアで購入可能です。
洗濯槽わかめの掃除 塩素系と酸素系の違い

洗濯槽わかめ対策の成功は、クリーナーの特性を正しく理解し、使い分けることにかかっています。「塩素系」と「酸素系」、どちらが優れているというわけではなく、それぞれに得意・不得意があります。
「塩素系」は、汚れやカビそのものを化学的に「分解・溶かす」アプローチです。例えるなら、カビ菌を根こそぎ殺菌する化学兵器のようなものです。
「酸素系」は、お湯の力で発泡し、こびりついた汚れを物理的に「剥がし取る」アプローチです。例えるなら、高圧洗浄機で汚れの塊を吹き飛ばすようなイメージです。
それぞれのメリット・デメリットを、再度比較表で詳しく確認しましょう。
| 種類 | 主成分 | 汚れの落とし方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 塩素系 (カビキラーなど) | 次亜塩素酸ナトリウム | カビを分解・溶かす | ・殺菌力が非常に高い ・汚れを溶かすため、すくう手間が不要 ・つけ置き時間が短い(または不要) ・冷水でも十分な効果を発揮 ・ドラム式洗濯機でも問題なく使える | ・特有のツンとした刺激臭(要換気) ・衣類に付着すると脱色(漂白)する ・酸性タイプと混ぜると有毒ガス発生(まぜるな危険) ・汚れが取れた実感は湧きにくい |
| 酸素系 (オキシクリーンなど) | 過炭酸ナトリウム | カビを発泡・剥がす | ・ニオイが穏やかで、刺激が少ない ・衣類や環境への負荷が比較的少ない ・剥がれ落ちる汚れを視認できる(達成感) ・石鹸カスや皮脂汚れにも強い | ・お湯(40~50℃)が必須(水では効果半減) ・長時間のつけ置きが必要(2~6時間) ・浮いたわかめをすくう手間が必須 ・ドラム式では使用不可の機種が多い |
【状況別:おすすめの使い分け】
- 数年間、一度も掃除していない場合:
まずは強力な殺菌力でカビ菌自体を叩くため、「塩素系」クリーナー(できればメーカー純正品)で徹底的に除菌することをおすすめします。パナソニックなどの多くの洗濯機メーカーも、基本のお手入れとして塩素系クリーナー(または衣類用塩素系漂白剤)の使用を推奨しています。(参照:パナソニック公式サイト 洗濯槽の黒カビ 予防と対策) - 1~2ヶ月に1度の定期メンテナンスの場合:
手軽に済ませたいなら「塩素系」、時間があり汚れを実感したいなら「酸素系」と、好みで選んでも良いでしょう。 - ドラム式洗濯機の場合:
選択肢はほぼ「塩素系」一択です。理由は次項で詳しく説明します。
【最重要】「まぜるな危険」の厳守
塩素系のクリーナー(次亜塩素酸ナトリウム)と、酸性タイプの製品(クエン酸、お酢、酸性洗剤など)が混ざると、人体に極めて有害な「塩素ガス」が発生します。これは命に関わる重大な事故につながります。
消費者庁も「塩素系の製品に『まぜるな危険』と表示されている酸性タイプの製品が混ざると、有毒な塩素ガスが発生して非常に危険です」と厳しく注意喚起しています。(出典:消費者庁 雑貨工業品品質表示規程)
「塩素系で掃除した後、水垢取りのためにすぐにクエン酸で掃除する」といった連続使用も、槽内に塩素成分が残っているとガスが発生する可能性があり、非常に危険です。絶対に同時に使ったり、間隔を空けずに連続で使ったりしないでください。
洗濯槽わかめの掃除にオキシクリーンは有効か
SNSを中心に「オキシ漬け」として絶大な人気を誇るオキシクリーン。これは酸素系漂白剤の代表的な商品であり、もちろん洗濯槽わかめの掃除にも有効です。
主成分の過炭酸ナトリウムが、40℃~50℃のお湯と反応することで爆発的な発泡力を生み出し、洗濯槽の裏側に長年こびりついたカビやヘドロ汚れを、ごっそりと剥がし落とします。「こんなに汚れた洗濯機で洗っていたのか…」と視覚的に衝撃を受けることができるため、掃除の達成感は非常に高いです。
しかし、オキシクリーンを使った洗濯槽掃除には、その効果と引き換えに、いくつかの重大な注意点(デメリット)が存在します。これを理解せずに使うと、失敗したり、最悪の場合は洗濯機を故障させたりする可能性があります。
1. 浮いてきた大量の「わかめ」をすくう手間
最大の難関がこれです。オキシクリーンは汚れを「溶かす」のではなく「剥がす」クリーナーです。そのため、つけ置き後、水面には想像を絶する量のわかめが浮かびます。このわかめを、前述したネットなどを使って、排水前に根気よく、何度もすくい取らなければなりません。
この作業を怠ると、わかめの塊が排水ホースや排水フィルターに詰まり、「排水エラー」で洗濯機が緊急停止し、修理業者を呼ぶ羽目になる…といった最悪の事態を招きかねません。
2. ドラム式洗濯機には原則NG(故障リスク)
これが最も重要な注意点です。オキシクリーンは非常に泡立ちやすい性質を持っています。節水構造であるドラム式洗濯機で使用すると、異常な量の泡が発生し、泡が洗濯機内部のセンサー(水位センサーなど)に付着して誤作動を起こしたり、ひどい場合には泡が機外に漏れ出したりして、故障の直接的な原因となります。
実際に、パナソニックや日立などの主要な洗濯機メーカーは、取扱説明書において「ドラム式洗濯機での酸素系漂白剤(洗濯槽クリーナーとして)の使用」を禁止または非推奨としています。万が一、オキシクリーンが原因で故障した場合、保証期間内であってもメーカー保証の対象外となる可能性が極めて高いです。
3. お湯(40~50℃)の準備が必須
オキシクリーンの洗浄効果(酵素パワー)が最大化されるのは40℃~60℃です。冷水ではその効果は半減以下になってしまいます。高水位までお湯を溜めるには、給湯器から直接給湯するか、バケツでお湯を何往復も運ぶ必要があり、かなりの手間がかかります。
結論として、オキシクリーンは、「縦型洗濯機」で、「時間と手間をかける覚悟」があり、「汚れが取れる達成感を味わいたい」場合にのみ適した方法と言えます。
ドラム式洗濯槽わかめの特有な取り方

ドラム式洗濯機は、構造的に縦型よりわかめ(カビ)が発生しにくいとはいえ、油断は禁物です。ドラム式には、ドラム式特有の汚れやすいポイントがあり、そこをピンポイントで対策する必要があります。
ドラム式のわかめ対策は、「①ドアパッキンの掃除」と「②槽洗浄(塩素系)」の二本立てで考えることが重要です。
1. 最重要:ドアパッキンの掃除(わかめの発生源)
ドラム式洗濯機で最もカビが発生しやすい場所、それが「ドア(フタ)のゴムパッキン」です。このパッキンは複雑な溝状になっており、洗濯のたびに水や洗剤カス、髪の毛、糸くずが溜まります。ここが常に湿った状態になるため、黒カビ(わかめ予備軍)の完璧な住処となります。
【日常のお手入れ】
洗濯が終了するたびに、乾いたタオルや雑巾で、パッキンの溝の内側をぐるりと一周拭き上げる習慣をつけてください。これだけで、カビの発生を劇的に抑えることができます。
【カビが発生してしまった場合】
もし既に黒カビが点々と発生してしまった場合は、塩素系カビ取り剤(キッチン泡ハイターやカビキラーなど)を使います。
- ゴム手袋を装着します。
- キッチンペーパーをこより状にし、カビが発生している溝に詰め込みます。
- そのキッチンペーパーめがけて、カビ取り剤をスプレーし、「カビ取りパック」の状態にします。
- 5分~10分ほど放置します。(※長時間放置するとゴムパッキンが劣化する可能性があるため注意)
- 時間が経ったらキッチンペーパーを取り除き、水で濡らして固く絞った雑巾で、カビ取り剤の成分が残らないよう何度も水拭きします。
- 最後に、乾いた布で水分を完全に拭き取ります。
2. 槽洗浄(塩素系クリーナーが基本)
パッキンをきれいにしたら、次は洗濯槽本体です。前述の通り、ドラム式洗濯機には、泡立ちの多い酸素系クリーナー(オキシクリーンなど)は故障のリスクがあるため使用できません。
必ず、メーカー純正のドラム式専用クリーナー(例:パナソニック N-W2)や、市販品であれば「ドラム式対応」と明確に記載された塩素系クリーナーを選んでください。
使用方法は非常に簡単で、クリーナーを洗濯槽に直接投入し、洗濯機の「槽洗浄コース」を選んでスタートボタンを押すだけです。ドラム式の槽洗浄コースは、多くの場合、温水を使ったり、時間をかけて(3時間~11時間など)洗浄したりする高機能なモードが搭載されており、効果的にカビを分解・除去してくれます。
排水フィルター掃除も洗濯槽わかめ対策に重要
洗濯槽の「中」ばかりに目が行きがちですが、わかめ対策において「出口」の掃除、すなわち「排水フィルター(糸くずフィルター)」の清掃は、槽洗浄と同じくらい重要です。
洗濯機の種類によって、このフィルターの名称と場所が異なります。
縦型洗濯機の場合:「糸くずフィルター」
洗濯槽の内部側面や、槽の上部フチについているネット状の部品です。ここには洗濯中に出た衣類の糸くずや髪の毛が溜まります。ここを掃除せずに放置すると、フィルター内で雑菌やカビが繁殖し、それが洗濯水に逆流して、わかめの発生や生乾き臭の原因となります。カビの温床そのものです。
ドラム式洗濯機の場合:「排水フィルター」
洗濯機本体の左下や右下にある、小さなカバーの中に隠されています。ここには糸くずだけでなく、洗濯槽洗浄で剥がれ落ちたわかめ(カビの塊)や、ポケットに入っていた小銭、ヘアピン、ボタンなどが溜まります。ここが詰まると、「排水エラー」が表示されて洗濯機が停止する原因になります。また、溜まったゴミがヘドロ状になり、強烈なニオイとカビの発生源となります。
これらのフィルターは、最低でも週に1回、理想を言えば洗濯のたびに掃除する習慣をつけてください。
特に、洗濯槽クリーナー(塩素系・酸素系問わず)を使って槽洗浄を行った直後は、剥がれたわかめが大量にこのフィルターに溜まっている可能性が非常に高いです。槽洗浄が終わったら、必ず排水フィルター(糸くずフィルター)もセットで点検し、清掃するように徹底してください。これを怠ることが「掃除したのにわかめが出る」原因の一つにもなっています。
洗濯槽わかめを予防しつかないようにする方法

一度、純正クリーナーなどで洗濯槽をリセットし、わかめを徹底的に除去できたなら、その状態をキープするための「予防」が何よりも重要です。カビ(わかめ)は、少し油断するとすぐにまた繁殖を始めます。
以下の「カビを寄せ付けない5つの習慣」を実践するだけで、わかめがつかないようにする効果が劇的に高まります。
1. 洗濯機のフタ(ドア)は常に開けておく
これが最も簡単で、最も効果的な予防策です。カビは湿気を何よりも好みます。洗濯終了後は、洗濯槽の内部を乾燥させるため、フタ(ドラム式の場合はドア)を常に開けておき、内部の湿気を逃がして乾燥させることを徹底してください。(※小さなお子様やペットがいるご家庭では、中に入り込まないよう、チャイルドロックをかける、浴室のドアを閉めるなどの安全対策を併用してください)。
2. 洗剤・柔軟剤は「適量」を厳守する
「汚れをしっかり落としたい」「良い香りをさせたい」という思いから、洗剤や柔軟剤を規定量よりも多く入れてしまうのは、カビに餌を与えているのと同じ行為です。溶け残った洗剤・柔軟剤は、カビの最高の栄養分となります。必ず製品に記載されている適量を守ってください。特に最近の濃縮タイプの液体洗剤は、キャップ半分でも入れすぎになることがあるため注意が必要です。
3. 洗濯物は溜め込まない(洗濯槽をカゴ代わりにしない)
脱いだ衣類や濡れたタオルを、洗濯機の中に直接溜めていくのは絶対にやめましょう。湿気と皮脂汚れが洗濯槽内に充満し、カビの繁殖を急速に促進させます。洗濯物は、必ず通気性の良い専用の洗濯カゴ(ランドリーバスケット)に入れてください。
4. 「槽乾燥」機能を定期的に活用する
乾燥機能付きの洗濯機(縦型・ドラム式問わず)をお持ちの場合、週に1回程度、衣類を入れずに「槽乾燥コース」を実行するのもカビ予防に非常に効果的です。カビは熱と乾燥に弱いため、定期的な加熱乾燥でカビ菌の繁殖を抑制できます。
5. 月に1度の「予防的」槽洗浄を行う
わかめが発生して(目に見えて)から慌てて掃除するのではなく、「発生する前」に定期的にメンテナンスを行うことが理想です。多くの洗濯機メーカーは、月に1回程度の「槽洗浄」を推奨しています。(参照:パナソニック公式サイト 洗濯槽の黒カビ 予防と対策)
この月1回のメンテナンスには、高価な純正クリーナーでなくても構いません。手軽な市販の衣類用塩素系漂白剤(ハイターなど)を規定量(例:水50Lに対し200ml程度)入れて、槽洗浄コース(または標準コース)を回すだけでも、カビの発生を抑える十分な予防効果があります。
まとめ:正しい洗濯槽わかめの取り方で清潔に
洗濯槽から出てくる不快な「わかめ」(黒カビ)の問題は、見た目の不快さだけでなく、衣類へのニオイ移りや、場合によってはアレルギーの原因にもなりかねない、衛生面での重大なサインです。
しかし、その原因と正しい対処法さえ知っていれば、決して解決できない問題ではありません。今回の記事で解説した「洗濯槽 わかめの 取り方」の重要なポイントを、最後にもう一度まとめます。
- わかめの正体は洗濯槽裏の黒カビと洗剤カス、皮脂汚れが混ざった塊
- わかめは「湿度」「栄養(洗剤カスなど)」「温度」が揃うと爆発的に繁殖する
- わかめは水が溜まる隙間が多い縦型洗濯機の方が出やすい傾向がある
- 塩素系クリーナーはカビを「分解・溶かす」ため、殺菌力が高く手間が少ない
- 酸素系クリーナー(オキシクリーン)は汚れを「剥がす」力が強く、達成感がある
- 酸素系は40~50℃のお湯が必須で、浮いた「わかめをすくうネット」作業も必須
- ドラム式洗濯機には泡が大量に出る酸素系(オキシクリーン)は故障の原因になるため使用しない
- ドラム式は槽洗浄(塩素系)とセットで「ドアパッキン」の掃除が特に重要
- 服についた取れないわかめは、慌てず「酸素系漂白剤」でつけ置きして取る
- 掃除したのにわかめが出るのは、汚れが根深く、一度で取りきれていない証拠
- 市販品でわかめが止まらない時は、メーカー純正の強力なクリーナーを試す価値あり
- 排水フィルターや糸くずフィルターの掃除も忘れずに。「槽洗浄直後」は必須
- 最大の予防策は、洗濯終了後にフタを開けて「乾燥」させること
- 洗剤や柔軟剤の入れすぎはカビの餌になるため、必ず「適量」を守る
- 月1回の手軽な槽洗浄(衣類用漂白剤でも可)で、わかめがつかないようにする予防が最も大切
しつこい洗濯槽のわかめも、ご家庭の洗濯機タイプと汚れの状況に合わせて、適切なクリーナーを選び、正しい手順で掃除すれば必ず撃退できます。そして何より、掃除後の清潔な状態をキープするための日々の「予防」こそが、わかめとの戦いに終止符を打つ鍵となります。今回の洗濯槽わかめの取り方を参考に、今日からぜひ実践して、清潔で快適な洗濯ライフを取り戻してください。